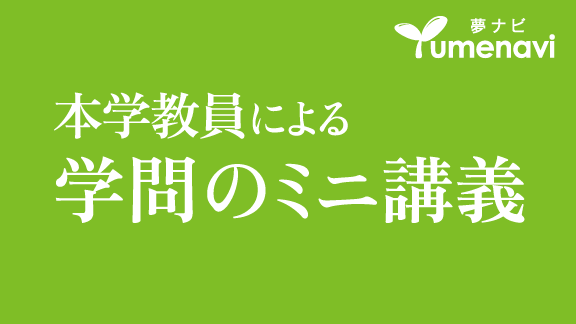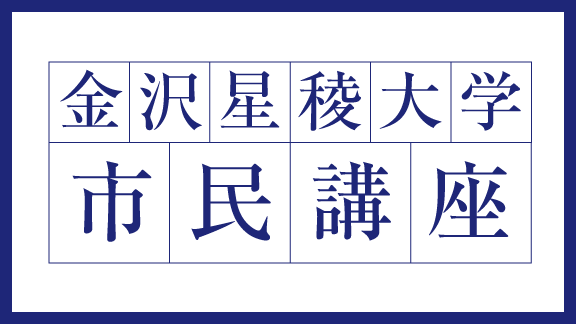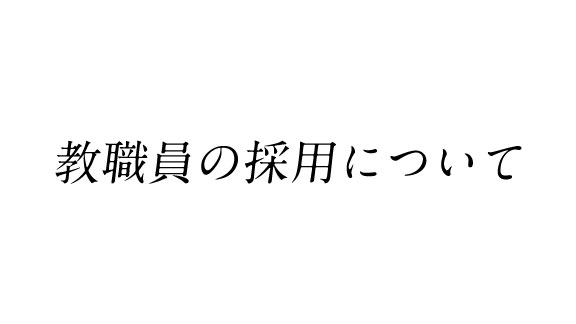学長コラム
能登応援メッセージ「今、能登復興に必要とされる星稜人材」
2024.08.01
本年1月1日の「能登半島地震」から、8か月目です。もう真夏、ほどなく秋も訪れます。 政府は4月の閣議で能登半島地震の被災地復興に向けた4回目の予備費の支出を決め、2024年度予算の予備費から仮設住宅の建設やインフラの復旧費用などに1389億円、応急仮設住宅の建設費などに683億円、土木施設や公共施設といったインフラの復旧費用に647億円、これまでに決まった支出と合わせると総額4100億円を上回るということですので、被災建物の公費解体とか、水道・道路・港湾の復旧などインフラ整備にも弾みがつくものと期待されます(日経新聞 2024年4月23日)。さらに、「復興基金」として石川県に520億円の財政支援を決めましたから、政府や県の財政面での支援はそれなりに手厚いと評価できるのではないでしょうか。
これらを受けて、石川県では、6月「石川県創造的復興プラン」を発表しました。
このプランでは創造的復興のスローガンとして、「能登が示す、ふるさとの未来」を掲げています。能登は私たちにとって特別なふるさとの地ですが、同時に日本が抱える様々な課題を先取りした「先進地」でもあります。1月1日の大震災の痛みと悲しみを乗り越え、新しい未来の姿につなげたい。そのような地域の姿を示すことは、能登はもとより、日本各地のそして世界中のあらゆる故郷・地域つくりの希望につながる先駆的な試みなのだという問題意識とスローガンに心から賛同し、エールを送りたいと思います。
続いて、「石川県創造的復興プラン」は施策の4つの柱を次のように掲げます。
1.教訓を踏まえた災害に強い地域づくり
2.能登の特色ある生業(なりわい)の再建
3.暮らしとコミュニティの再建
4.誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり
これらの中から、創造的復興を象徴するプロジェクトを「創造的復興リーディングプロジェクト」として13の取り組みを例示しています。1復興プロセスを活かした関係人口の拡大、2能登サテライトキャンパス構想の推進、3能登に誇りと愛着が持てるような「学び」の場づくり、4新たな視点に立ったインフラの強靭化、5自立・分散型エネルギーの活用などグリーンイノベーションの推進、6のと里山空港の拠点機能の強化、7利用者目線に立った持続可能な地域公共交通、8奥能登版デジタルライフラインの構築、9能登の「祭り」の再興、10震災遺構の地域資源化に向けた取り組み、11能登半島国定公園のリ・デザイン、12トキが舞う能登の実現、13産学官が連携した復興に向けた取組みの推進、です。
巨額の予算に裏付けられ、4つの基本施策と13の「リーディングプロジェクト」に体系化され整理された「石川県創造的復興プラン」ですから、今後その実現は着実に進められると期待するのですが、珠洲市で被災された本学名誉教授澤信俊先生は、「足りないものがある」と顔を曇らせます。4つの基本施策、13の「リーディングプロジェクト」は言ってみれば縦糸、これらの一つ一つはよく考えられていて専門性が高いと評価しているのですが、これらを横糸で結びつけ、復興に取り組む役割の「人」の姿が見えないというのです。「人間の創造的復興」を提唱している澤先生ならではの指摘です。
例えば珠洲市の地豆腐「大浜大豆・豆腐」は、里山の恵み「大浜大豆」と、里海の揚げ浜式塩田が生み出した「天然にがり」の二つが結ばれて、はじめて美味しい豆腐が生まれる。能登の里山里海、この陸と海の構造が理解されずに、他産地の原料と製造設備だけ導入しても本物の「大浜大豆・豆腐」にならない。
被災地も被災者も時間や季節の移り変わりと共に、置かれた状況が刻々と変化します。時にはそしてしばしば、何が問題なのか、当事者ですら、いや当事者であるがゆえに分からないことがあるというのです。当事者は困ってはいるが、それがどうしてなのか全体が見えず、どうしたら解決できるかも見えないものだから、手探りのまま、我慢を強いられてしまう。学問の世界でも、本当に分からない時には、何が分からないのかが分からない。結果としてうまくいかないという事態に陥りますね。澤先生のおっしゃっていることもそのようなものであろうと思います。もちろん縦糸を軸とする様々な専門分野の専門人材は不可欠なのですが、現場に立ち合って地域の人々に寄り添い、現状を把握しながら、問題に気づき、たいていそれは複合的な場合が多いでしょうから、それらを整理していくつかの解決可能な下位の課題に設定し直し、解決に導こうとする横糸人材が必要なのだと。この縦糸と横糸が織なって、はじめて強靭な布になる。
そのお話を伺いながら、かつて教育学部に勤務していた時のエピソードを思い起こしました。一流上場企業の人事担当者がしばしば教育学部生の採用に訪れるのです。医師養成と教員養成はきわめて目的的な人材養成教育なので、一般企業人材に必要な経済や経営、法律的な知識はないかもしれないと、話しを聞いてみると、その人事担当者は思いもかけないことを言います。
その企業では、法・経・理・工など多様な大学・学部・学科から数グループ単位でリクルートするのだそうですが、一グループの中に教育学部出身者がいると、その人は様々な分野を超えて幅広く学んでいるし、心理学や教職教養なども身に付いているので、誰とでも話ができ、グループ内の相互の人材を結び付ける触媒の役割を果たしてくれるというのです。
金沢星稜大学は、日経キャリアマガジン2022・23就職力ランキング小規模大学部門で総合1位に選ばれ、ことに「行動力」、「対人力」、「独創性」が高いと評価された、もともと現場対応力の高い学生を育ててきました。
また、能登では北前船の航海や運用、日本酒などの醸造や発酵、炭焼きや鉱山開発、珠洲焼、輪島塗など、様々な分野をカバーする多角経営の地であった長い歴史があります。輪島市町野川沿いにある「時国家」などは、単なる農家の範疇に収まらず、数艘の大きな船を所有し、松前から、佐渡、敦賀、京、大阪と交流し、塩、材木、炭などを運び、鉱山経営に至るまで多角経営を行っていた廻船交易業者であったことが明らかになっています。私たちのご先祖は、文理融合とかSTEAM-Dといった言葉がなかった時代から、すでにそのような営みを営々と築き上げていたことが分かります。
能登の創造的復興を支える人材として今必要とされているのは、能登地域の自然や地理、農業や漁業、自然科学やデジタル・トランスフォーメーションの知識・技能を持ち、歴史や文化まで理解している文理融合・総合的な人材であり、現場で問題に対応できるまさに「星稜人材」なのではないでしょうか。
これらを受けて、石川県では、6月「石川県創造的復興プラン」を発表しました。
このプランでは創造的復興のスローガンとして、「能登が示す、ふるさとの未来」を掲げています。能登は私たちにとって特別なふるさとの地ですが、同時に日本が抱える様々な課題を先取りした「先進地」でもあります。1月1日の大震災の痛みと悲しみを乗り越え、新しい未来の姿につなげたい。そのような地域の姿を示すことは、能登はもとより、日本各地のそして世界中のあらゆる故郷・地域つくりの希望につながる先駆的な試みなのだという問題意識とスローガンに心から賛同し、エールを送りたいと思います。
続いて、「石川県創造的復興プラン」は施策の4つの柱を次のように掲げます。
1.教訓を踏まえた災害に強い地域づくり
2.能登の特色ある生業(なりわい)の再建
3.暮らしとコミュニティの再建
4.誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり
これらの中から、創造的復興を象徴するプロジェクトを「創造的復興リーディングプロジェクト」として13の取り組みを例示しています。1復興プロセスを活かした関係人口の拡大、2能登サテライトキャンパス構想の推進、3能登に誇りと愛着が持てるような「学び」の場づくり、4新たな視点に立ったインフラの強靭化、5自立・分散型エネルギーの活用などグリーンイノベーションの推進、6のと里山空港の拠点機能の強化、7利用者目線に立った持続可能な地域公共交通、8奥能登版デジタルライフラインの構築、9能登の「祭り」の再興、10震災遺構の地域資源化に向けた取り組み、11能登半島国定公園のリ・デザイン、12トキが舞う能登の実現、13産学官が連携した復興に向けた取組みの推進、です。
巨額の予算に裏付けられ、4つの基本施策と13の「リーディングプロジェクト」に体系化され整理された「石川県創造的復興プラン」ですから、今後その実現は着実に進められると期待するのですが、珠洲市で被災された本学名誉教授澤信俊先生は、「足りないものがある」と顔を曇らせます。4つの基本施策、13の「リーディングプロジェクト」は言ってみれば縦糸、これらの一つ一つはよく考えられていて専門性が高いと評価しているのですが、これらを横糸で結びつけ、復興に取り組む役割の「人」の姿が見えないというのです。「人間の創造的復興」を提唱している澤先生ならではの指摘です。
例えば珠洲市の地豆腐「大浜大豆・豆腐」は、里山の恵み「大浜大豆」と、里海の揚げ浜式塩田が生み出した「天然にがり」の二つが結ばれて、はじめて美味しい豆腐が生まれる。能登の里山里海、この陸と海の構造が理解されずに、他産地の原料と製造設備だけ導入しても本物の「大浜大豆・豆腐」にならない。
被災地も被災者も時間や季節の移り変わりと共に、置かれた状況が刻々と変化します。時にはそしてしばしば、何が問題なのか、当事者ですら、いや当事者であるがゆえに分からないことがあるというのです。当事者は困ってはいるが、それがどうしてなのか全体が見えず、どうしたら解決できるかも見えないものだから、手探りのまま、我慢を強いられてしまう。学問の世界でも、本当に分からない時には、何が分からないのかが分からない。結果としてうまくいかないという事態に陥りますね。澤先生のおっしゃっていることもそのようなものであろうと思います。もちろん縦糸を軸とする様々な専門分野の専門人材は不可欠なのですが、現場に立ち合って地域の人々に寄り添い、現状を把握しながら、問題に気づき、たいていそれは複合的な場合が多いでしょうから、それらを整理していくつかの解決可能な下位の課題に設定し直し、解決に導こうとする横糸人材が必要なのだと。この縦糸と横糸が織なって、はじめて強靭な布になる。
そのお話を伺いながら、かつて教育学部に勤務していた時のエピソードを思い起こしました。一流上場企業の人事担当者がしばしば教育学部生の採用に訪れるのです。医師養成と教員養成はきわめて目的的な人材養成教育なので、一般企業人材に必要な経済や経営、法律的な知識はないかもしれないと、話しを聞いてみると、その人事担当者は思いもかけないことを言います。
その企業では、法・経・理・工など多様な大学・学部・学科から数グループ単位でリクルートするのだそうですが、一グループの中に教育学部出身者がいると、その人は様々な分野を超えて幅広く学んでいるし、心理学や教職教養なども身に付いているので、誰とでも話ができ、グループ内の相互の人材を結び付ける触媒の役割を果たしてくれるというのです。
金沢星稜大学は、日経キャリアマガジン2022・23就職力ランキング小規模大学部門で総合1位に選ばれ、ことに「行動力」、「対人力」、「独創性」が高いと評価された、もともと現場対応力の高い学生を育ててきました。
また、能登では北前船の航海や運用、日本酒などの醸造や発酵、炭焼きや鉱山開発、珠洲焼、輪島塗など、様々な分野をカバーする多角経営の地であった長い歴史があります。輪島市町野川沿いにある「時国家」などは、単なる農家の範疇に収まらず、数艘の大きな船を所有し、松前から、佐渡、敦賀、京、大阪と交流し、塩、材木、炭などを運び、鉱山経営に至るまで多角経営を行っていた廻船交易業者であったことが明らかになっています。私たちのご先祖は、文理融合とかSTEAM-Dといった言葉がなかった時代から、すでにそのような営みを営々と築き上げていたことが分かります。
能登の創造的復興を支える人材として今必要とされているのは、能登地域の自然や地理、農業や漁業、自然科学やデジタル・トランスフォーメーションの知識・技能を持ち、歴史や文化まで理解している文理融合・総合的な人材であり、現場で問題に対応できるまさに「星稜人材」なのではないでしょうか。
 筆者撮影 夏が来た、まもなく秋が訪れる:ハス寺・持明院(金沢市)の妙蓮
筆者撮影 夏が来た、まもなく秋が訪れる:ハス寺・持明院(金沢市)の妙蓮