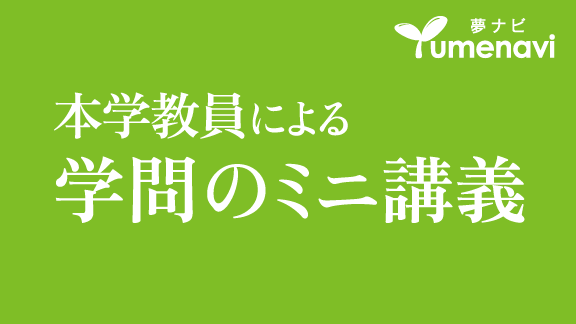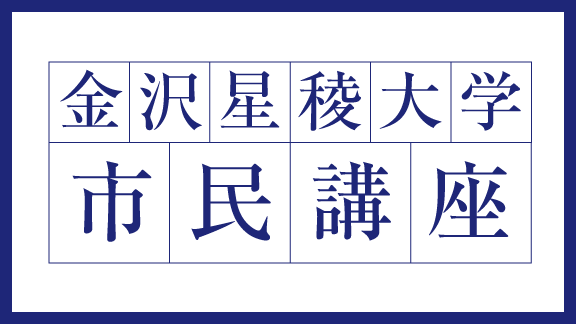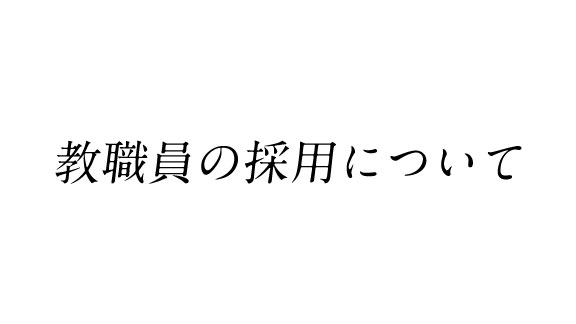トピックス
【金沢星稜大学市民講座】(第105回)「「通夜」本来の深い意味を知る」を開催しました
2024.12.16

10/19(土)
バイヤー・アヒム人文学部教授が、標題のテーマで講座を行いました。
通夜・葬儀は、通過儀礼と言われ、人々の生涯における誕生・成人・結婚・死亡といった節目を通過する際に行なわれる儀礼のことを指しますが、ある意味では人としての成長の機会と捉えて、人生の一部と見なしてもよいかもしれません。また、死生観について学べる機会であり、たいへん有意義な場であるとも言えます。
さて、現代日本語で「通夜」として知られる表現は、もともと一晩中続く儀式を指していました。友人や親族が故人の家やお寺に集まり、多くの人が夜を通して起きていました。この伝統的な習慣は、共同体の精神や家族の絆を深めるものでした。起きていることを暗闇に対する勝利であるとし、故人も死に打ち勝ち、より良い往生の地へ旅立つことを願いました。また、友人や親族が故人と共に暗闇を抜け、再び光が差すまで寄り添うという意味もあったのです。

京都近くの比叡山では、「常行三昧」という修行者が数日間眠らずに阿弥陀仏に祈り続ける特別な修行が行われています。浄土宗と浄土真宗の教組である法然上人や親鸞聖人も若い頃にこの修行を行ったと言われています。修行者が数日間眠らずにいることで、特別な心の状態に入るとされており、インド仏教では、この修行が世界全体を幻影、または「唯心」として見る理由の一つとされていました。また、釈迦が80歳ごろに森で弟子を囲み最後の言葉として「諸行無常」と言われ、死後は、盛大な葬儀が行われ、七日七夜も寝ないで弔ったといわれます。
「通夜」は通過儀礼であると同時に親族間の絆を強めたり、伝統を守る役目も果たしているとし、講座をしめくくりました。
「通夜」がもつ意味についてのほか、通夜の歴史的な経緯と今日の通夜との共通点などを知っていただけたのではないでしょうか。
「通夜」は通過儀礼であると同時に親族間の絆を強めたり、伝統を守る役目も果たしているとし、講座をしめくくりました。
「通夜」がもつ意味についてのほか、通夜の歴史的な経緯と今日の通夜との共通点などを知っていただけたのではないでしょうか。