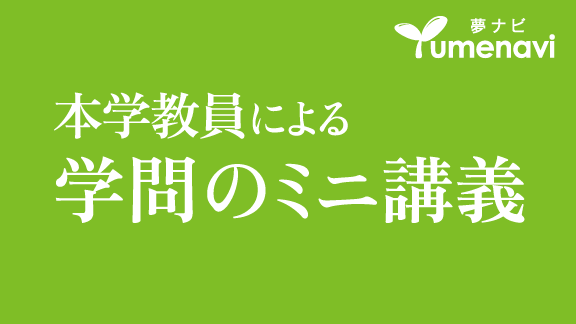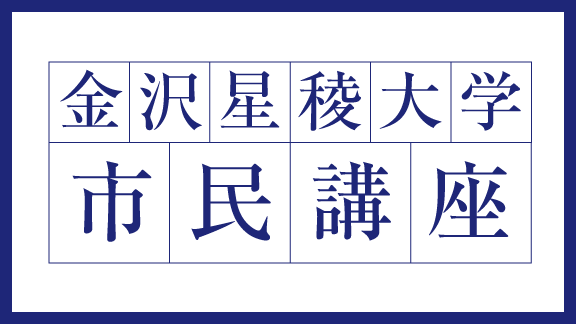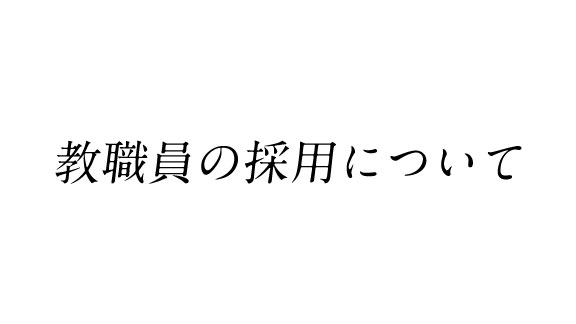地域連携
【地域連携/ボランティア】穴水町と輪島市の保育所3園に“楽しい!”をお届けしました!
2025.11.26
11/5(水)・6(木)
学生が主体となり、令和6年能登半島地震において被災した保育所の子どもたちや職員の方々がフフッと笑えるような“楽しい時間”を少しでも提供できないかと考え、今回はできるだけ多くの子どもたちや職員の方々に届けるため、2日間にわたり計3園を訪問しました。
1日目の午前中には穴水町にある光琳寺保育所、午後には神杉保育所を訪問。音楽を用いた劇「おおきなかぶ(+さつまいもVer.)」を披露し、給食を一緒に食べさせていただいたり、おやつを一緒に食べさせていただいたりしました。
2日目には、輪島市にあるもんぜん児童館において輪島市立松風台保育所の子どもたちに会いに行きました。ホールの修繕が終わっていない園であったため、体を思い切り動かせるように児童館をお借りして活動しました。
今回の訪問では、園長先生から震災の影響はまだまだ続いていることなどをお聞きしました。一方で大変嬉しい直筆の手紙もいただきました。その手紙には「子どもたちが無邪気に過ごすことができました。それは貴方達が無邪気な世界が好きだし、楽しむことを知っているからです。子どもたちをその世界に誘ってくれたからです。感謝申し上げます。園長。」と書かれていました。
2日目には、輪島市にあるもんぜん児童館において輪島市立松風台保育所の子どもたちに会いに行きました。ホールの修繕が終わっていない園であったため、体を思い切り動かせるように児童館をお借りして活動しました。
今回の訪問では、園長先生から震災の影響はまだまだ続いていることなどをお聞きしました。一方で大変嬉しい直筆の手紙もいただきました。その手紙には「子どもたちが無邪気に過ごすことができました。それは貴方達が無邪気な世界が好きだし、楽しむことを知っているからです。子どもたちをその世界に誘ってくれたからです。感謝申し上げます。園長。」と書かれていました。

自分たちにできることをしようと、小さなことかもしれませんが、少しずつ活動を重ねてきました。この小さな継続に対してこのようなお言葉をいただき、嬉しさをみんなで噛み締めました。そして私たちだからこそ担える役割があるのだと、今後の活動への思いを強く持つ機会となりました。光琳寺保育所、神杉保育所、松風台保育所の皆さま、楽しい時間を、そしてあたたかい言葉を、本当にありがとうございました。
(文:担当教員 連 桃季恵)
学生のコメント
人間科学部こども学科 3年次 M・Rさん(石川県 金沢西高等学校出身)
訪問した園で給食を一緒に食べさせていただいた時、先生から震災が起きてから給食がどのように変化したのかを教えて頂きました。最初の頃は富山から食材を調達して献立を作っていたけど、今は農協(JA)さんの協力のもと野菜を調達しているということを知りました。魚の調達が難しい中、漁師さんたちとの繋がりから今ではお味噌汁やサラダにお魚を入れることが出来るようになったということでした。
震災から間もなく2年が経とうとしていますが、まだまだ食材の確保が難しく、栄養バランスの整った給食を提供することが難しいという現状を知りました。普段当たり前のように食材を買い、栄養のある食事を取ることが出来ている日常はとても恵まれているということを実感しました。生産者さんへの感謝、その場にいる大切な人たちへの感謝、食べることが出来ることへの感謝などたくさんのものや人への感謝を忘れず、心を込めて「いただきます」ということの大切さを身をもって感じることが出来ました。
訪問した園で給食を一緒に食べさせていただいた時、先生から震災が起きてから給食がどのように変化したのかを教えて頂きました。最初の頃は富山から食材を調達して献立を作っていたけど、今は農協(JA)さんの協力のもと野菜を調達しているということを知りました。魚の調達が難しい中、漁師さんたちとの繋がりから今ではお味噌汁やサラダにお魚を入れることが出来るようになったということでした。
震災から間もなく2年が経とうとしていますが、まだまだ食材の確保が難しく、栄養バランスの整った給食を提供することが難しいという現状を知りました。普段当たり前のように食材を買い、栄養のある食事を取ることが出来ている日常はとても恵まれているということを実感しました。生産者さんへの感謝、その場にいる大切な人たちへの感謝、食べることが出来ることへの感謝などたくさんのものや人への感謝を忘れず、心を込めて「いただきます」ということの大切さを身をもって感じることが出来ました。

人間科学部こども学科 3年次 M・Mさん(石川県 野々市明倫高等学校出身)
2日目に訪問した保育所の子どもたちとは、児童館でパラバルーンをしました。その保育所は、ホールが地震によって崩れてしまったため、子どもたちの身体遊びができるように児童館を活用しました。そこではパラバルーンを行った後に「やきいもグーチーパー」で手や足を使ってじゃんけんをしたり、スカーフを使っておばけになったりと様々な遊びで子どもたちと関わり、子どもたちの笑顔溢れる姿を見て来てよかったなと感じました。
その後炊き出しを行っている施設を訪問する機会がありました。炊き出しに行ったのは初めてでどんな風にやっているんだろうとドキドキしながら行くと、地域の方々の集まりのような温かさがあり、小規模だからこそいろんな方とお話できる形になっていて、このようにして交流を深めていくんだなと感じました。今回の活動では、能登の現状を知り、保育所、保育園ではどのような環境に置かれているのかを知ることが出来ました。このような貴重な機会を大切にして学びに変えていきたいと思いました。
2日目に訪問した保育所の子どもたちとは、児童館でパラバルーンをしました。その保育所は、ホールが地震によって崩れてしまったため、子どもたちの身体遊びができるように児童館を活用しました。そこではパラバルーンを行った後に「やきいもグーチーパー」で手や足を使ってじゃんけんをしたり、スカーフを使っておばけになったりと様々な遊びで子どもたちと関わり、子どもたちの笑顔溢れる姿を見て来てよかったなと感じました。
その後炊き出しを行っている施設を訪問する機会がありました。炊き出しに行ったのは初めてでどんな風にやっているんだろうとドキドキしながら行くと、地域の方々の集まりのような温かさがあり、小規模だからこそいろんな方とお話できる形になっていて、このようにして交流を深めていくんだなと感じました。今回の活動では、能登の現状を知り、保育所、保育園ではどのような環境に置かれているのかを知ることが出来ました。このような貴重な機会を大切にして学びに変えていきたいと思いました。
人間科学部こども学科 3年次 N・Kさん(石川県 金沢伏見高等学校出身)
今回は2日で3つの園に行きました。どこの子どもたちも元気いっぱいでした。パラバルーンをして波を作っている時に「津波みたい」と言っている子がいて、2年前の出来事でも鮮明に覚えているのかもしれません。私は他の星稜ボランティアに参加しているのですが、そこで出会ったさつまいも農家の方がたまたま行った園に子どもを預けられていたようでお会いすることができ、いろんな繋がりを感じました。
能登に行く道を通る度、被災した道や家などが2年前とほとんど変わらない状態で、いつも過ごしている金沢では地震があったことを忘れるくらいの生活をしているけど、現地の人達は今もまだ戦っているということを感じます。私にできる支援をこれからも続けていきたいです。
今回は2日で3つの園に行きました。どこの子どもたちも元気いっぱいでした。パラバルーンをして波を作っている時に「津波みたい」と言っている子がいて、2年前の出来事でも鮮明に覚えているのかもしれません。私は他の星稜ボランティアに参加しているのですが、そこで出会ったさつまいも農家の方がたまたま行った園に子どもを預けられていたようでお会いすることができ、いろんな繋がりを感じました。
能登に行く道を通る度、被災した道や家などが2年前とほとんど変わらない状態で、いつも過ごしている金沢では地震があったことを忘れるくらいの生活をしているけど、現地の人達は今もまだ戦っているということを感じます。私にできる支援をこれからも続けていきたいです。