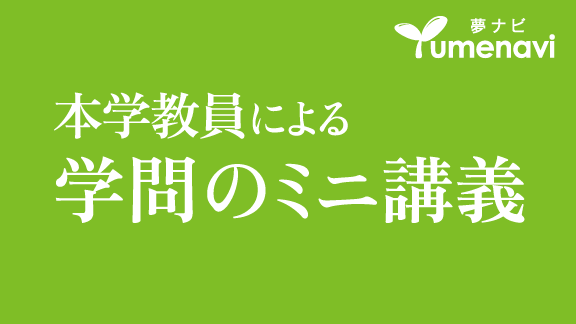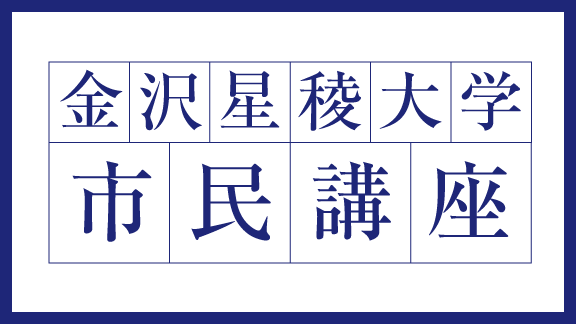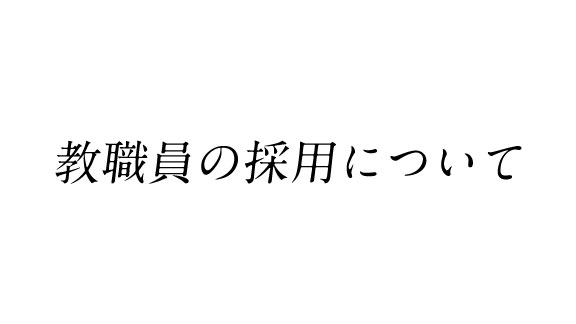学長コラム
「本当の自分に出会う」(令和7年度4月2日 入学式式式辞から)
2025.04.02
金沢の桜も満開を迎えようとしています。金沢星稜大学ならびに大学院に入学された皆さん。おめでとうございます。これまでの皆さんのご努力に敬意を表しますとともに、皆さんを支えてこられましたご家族や関係者の皆様にお祝いを申し上げます。
私が尊敬する、霊長類の研究者、元京都大学総長・山極壽一(やまぎわ・じゅいち)先生は、「大学はジャングルだ」と例えられました。ジャングルのある熱帯雨林は、世界中で最も生物多様性に富み、多様な生物が独自のニッチ(生態的居場所、すきま)を持ちつつひしめき合い、常に新しい種やニッチを生み出し、変化し、それでいて安定を保っています。しかも単独で成り立っているのではなく、赤道直下の豊富な太陽光と雨量によって支えられ、ジャングルと外の世界が有機的に結びついているというのです。
大学という所も同様で、多様な学問分野に研究者や学生がひしめき合い、分野の枠を超えて切磋琢磨することで、常に新しい考えや技術が生まれます。そのひしめき合う仲間に皆さんが加わることをジャングルの代表者として心から歓迎いたします。豊富な太陽光と雨量に匹敵するエネルギーは、大学の場合、社会の人々から寄せられる期待と願い、そして皆さんの若さと意欲、そして具体的な支援です。大学も社会も、常にそこを出入りする人間や情報を通して、互いにつながっているのですね。これが高校までとは違う、大学という学びの場の大きな特色です。
先ほど本学吹奏楽部の演奏、ミュージックサークルの皆さんの合唱で、学歌「白山(しらやま)の虚空を翔ける」をお聞きいただきました。学歌は建学の理念を謳います。お気づきのように、1番から3番の歌詞で、リフレインされるのが「経世こそはわれらの思念、済民こそはわれらが願い」という言葉です。「経世済民」。縮めて「経済」。エコノミクスの訳語になりましたが、もともとは世を経(おさ)め、民を済(すく)うという意味で、中国の古典に由来します。分かり易く言うと、「世の中で真面目に働いて暮らしを立てていく、さらにそれが自分だけでなく、ほかの人々の幸せや世の中に役立つようにしたい」という意味です。
このように「経世済民」は、経済学部はもとより、金沢星稜大学の全学部・全学科の礎となる建学の精神です。現在は「誠実にして社会に役立つ人間の育成」と分かり易く定式化されております。そしてやがて世界の人々の経世と済民とにまで思いを及ぼしたいものです。
金沢星稜大学が「誠実にして社会に役立つ人間の育成」という時、忘れてならない、あるいは特別に想いを寄せなければならないのは、能登半島という地域・社会です。
2024年元日の令和6年能登半島地震、そして同年9月には奥能登豪雨に見舞われました。まさに多重被災です。石川県においては、「創造的復興プラン」が立案され、現在その計画に従って懸命に復旧・復興が進められております。金沢星稜大学でも2024年から5年間の中期計画目標中に「能登半島地震の創造的復興とともに歩む」と明記し、能登支援のため「創造的復興論」の全学開講、能登にどのような新しい社会を作り上げたらよいのかを模索する活動を、様々なゼミや活動等を通して活発に展開しているところです。能登の復旧・復興がまだまだ道半ばであり、多くの人々が今なお苦しんでいることは皆さんご存知の通りです。しかしそうした状況にあって、今、いくつかの新しい動きが全国から注目されています。
それは「共助資本主義」と呼ばれています。2023年に、経団連が提唱し始めた新しい経済や社会の在り方を示す概念です。現在、私たちが生きている世界には、気候変動、自然災害、生物多様性の損失、国際紛争、飢餓、貧困、格差など、様々な課題が山積しています。これまで私たちは、個人や個々の企業が、物質的・経済的発展を追求することで、全体として人々が豊かになり、幸せになると考えてきましたが、これだけでは人類のさらなる繁栄や幸福が実現できないことに気が付き始めています。
これまでの企業や株主の利益を主眼にした従来型の資本主義に対して、社会の様々な企業体や関係者が連携し、共に助け合いながら、社会課題を解決する社会を作ることを目指そうというのが「共助資本主義」です。この概念は大学などの教育・研究機関にも大きな賛同を呼び、2025年2月には東京大学、大阪大学、一橋大学など13の大学が加盟した「共助資本主義の実現に向けた大学連合」(SOLVE!)が結成されました。本学もいつかはその一翼を担いたいと私は考えております。
なぜかというと、その「共助資本主義」の象徴的な事例が、能登半島・石川県地域に出現しているからです。
2024年、元旦「能登半島地震」で奥能登の3つの市町にある11の酒蔵はいずれも大きな被害を受け、昨年の酒造りは絶望的と言われました。ところが、3月から初夏にかけて、いつもとは違う形ですが、新酒が出来上がりました。まさに奇跡です。この奇跡は、金沢市、白山市、小松市、加賀市などの同業酒造会社の皆さんが、県外の長野県や宮城県の酒蔵にも呼び掛け、被災した能登の蔵から日本酒のもととなる「酒米」や「もろみ」を引き取り、協同で製造を代行し、また元に戻し、資金の提供も行って完成させたものでした。
その中の一つ、昨年6月に発売された白山市車多(しゃた)酒造と珠洲市の櫻田酒造の共助を見てみましょう。瓶のラベルには「能登の酒蔵復興応援」と朱書され、「能登大慶×天狗舞」の銘柄表示があります。おまけに豊漁を意味する「大慶」と、大漁を喜んで舞い踊る天狗の姿が青い海の色で印象深く描かれています。左下には小さく製造者として車多酒造の名が記され、その裏側には全壊した櫻田酒造の瓦礫の上に立ち、「新櫻田酒造建設予定地」と段ボールに手書きした看板と櫻田酒造の銘柄「能登初桜」を手に、再建を誓う櫻田博克氏の写真と、協同醸造に至った経緯、利益は櫻田酒造復興に充てられる旨が短く書かれています。私はこのラベルに深い感動を覚えました。
資本主義下近代経営学の世界ではライバル会社の不運はいわば自社のビジネスチャンスとなり、企業合併や買収(M&A)によって企業展開が進行すると考えられています。しかし能登の被災酒造家さんたちをめぐる共助活動はこれとは全く異なる発想・思想のもとに展開されているように見えます。これが「共助資本主義」です。今や能登は壮大な「共助資本主義」の実験場として全国から注目されるところとなっています。
皆さん、私は多くの皆さんが今はまだ何をしたらよいかが分からないけれど、いつか自分たちの手で社会をより良くしたい、と考えておられる方が増えてきていると実感しています。昨年1月、能登半島支援の学生ボランティアを募ったところ、2日間であっという間に135名の学生の皆さんから登録申し込みをいただきました。ありがたく、また尊いことです。皆さんも同様であろうと思います。目の前にある身近な問題から、地球規模の課題に至るまで、見てみぬふりをして背を向けるのではなく、できることから取り組んでまいりましょう。金沢星稜大学では、そのように考え、行動しようとする学生諸君を応援し、様々なプログラムや機会を提供します。
本日は、入学のお祝いを兼ねて、皆さんお一人おひとりに4年間の宿題を課したいと思います。それはこれからの4年間を、「生涯をかけても出会わなければならない人に出会うための準備の4年間にしなさい」ということです。 生涯をかけても出会わなければならない人、それは恋人かと思われた方も多いかもしれません。それも大事なことですが、私の言っているのは「本当の自分」ということです。
本当の自分と出会う、あるいは見つけるためにはどうしたらよいのでしょうか。それには、他者を知ることが不可欠です。学部や学科、勉強する学問の性格、学風によっても考え方や人間性に違いが出てきます。先生や友人、皆そうです。人は皆、他者との触れ合いの中で、この人は自分と違う、自分にはないものを持っていると気づかされます。そこから、他者をコピーするのではなく、参考にしながら、それまでの自分にはなかった新たな自分を描き、自分を超えようとします。
これからの4年間、あなた方一人ひとりが、自分の殻に閉じこもるのではなく、積極的に他者とかかわり、地域に出かけ、自分を表現してみてください。ただし、自分の宣伝や押しつけの必要はありません。
冒頭に大学はジャングルだと申し上げました。本学は多様性に富んださまざまな人間集団であります。あなた方の多感な4年間に、多様な考え方や人間に触れ、自分を高め、本当の自分に出会うことができる契機になるとすれば、それは一生の宝物になります。
結びに、皆さんが、金沢御所町の自然豊かなキャンパス環境で、充実した教育プログラムと先生方の指導、切磋琢磨する仲間たちとともに、将来に向けた様々な力を身につけ、「誠実にして社会に役立つ人間」になるための学びを深められますように。
私が尊敬する、霊長類の研究者、元京都大学総長・山極壽一(やまぎわ・じゅいち)先生は、「大学はジャングルだ」と例えられました。ジャングルのある熱帯雨林は、世界中で最も生物多様性に富み、多様な生物が独自のニッチ(生態的居場所、すきま)を持ちつつひしめき合い、常に新しい種やニッチを生み出し、変化し、それでいて安定を保っています。しかも単独で成り立っているのではなく、赤道直下の豊富な太陽光と雨量によって支えられ、ジャングルと外の世界が有機的に結びついているというのです。
大学という所も同様で、多様な学問分野に研究者や学生がひしめき合い、分野の枠を超えて切磋琢磨することで、常に新しい考えや技術が生まれます。そのひしめき合う仲間に皆さんが加わることをジャングルの代表者として心から歓迎いたします。豊富な太陽光と雨量に匹敵するエネルギーは、大学の場合、社会の人々から寄せられる期待と願い、そして皆さんの若さと意欲、そして具体的な支援です。大学も社会も、常にそこを出入りする人間や情報を通して、互いにつながっているのですね。これが高校までとは違う、大学という学びの場の大きな特色です。
先ほど本学吹奏楽部の演奏、ミュージックサークルの皆さんの合唱で、学歌「白山(しらやま)の虚空を翔ける」をお聞きいただきました。学歌は建学の理念を謳います。お気づきのように、1番から3番の歌詞で、リフレインされるのが「経世こそはわれらの思念、済民こそはわれらが願い」という言葉です。「経世済民」。縮めて「経済」。エコノミクスの訳語になりましたが、もともとは世を経(おさ)め、民を済(すく)うという意味で、中国の古典に由来します。分かり易く言うと、「世の中で真面目に働いて暮らしを立てていく、さらにそれが自分だけでなく、ほかの人々の幸せや世の中に役立つようにしたい」という意味です。
このように「経世済民」は、経済学部はもとより、金沢星稜大学の全学部・全学科の礎となる建学の精神です。現在は「誠実にして社会に役立つ人間の育成」と分かり易く定式化されております。そしてやがて世界の人々の経世と済民とにまで思いを及ぼしたいものです。
金沢星稜大学が「誠実にして社会に役立つ人間の育成」という時、忘れてならない、あるいは特別に想いを寄せなければならないのは、能登半島という地域・社会です。
2024年元日の令和6年能登半島地震、そして同年9月には奥能登豪雨に見舞われました。まさに多重被災です。石川県においては、「創造的復興プラン」が立案され、現在その計画に従って懸命に復旧・復興が進められております。金沢星稜大学でも2024年から5年間の中期計画目標中に「能登半島地震の創造的復興とともに歩む」と明記し、能登支援のため「創造的復興論」の全学開講、能登にどのような新しい社会を作り上げたらよいのかを模索する活動を、様々なゼミや活動等を通して活発に展開しているところです。能登の復旧・復興がまだまだ道半ばであり、多くの人々が今なお苦しんでいることは皆さんご存知の通りです。しかしそうした状況にあって、今、いくつかの新しい動きが全国から注目されています。
それは「共助資本主義」と呼ばれています。2023年に、経団連が提唱し始めた新しい経済や社会の在り方を示す概念です。現在、私たちが生きている世界には、気候変動、自然災害、生物多様性の損失、国際紛争、飢餓、貧困、格差など、様々な課題が山積しています。これまで私たちは、個人や個々の企業が、物質的・経済的発展を追求することで、全体として人々が豊かになり、幸せになると考えてきましたが、これだけでは人類のさらなる繁栄や幸福が実現できないことに気が付き始めています。
これまでの企業や株主の利益を主眼にした従来型の資本主義に対して、社会の様々な企業体や関係者が連携し、共に助け合いながら、社会課題を解決する社会を作ることを目指そうというのが「共助資本主義」です。この概念は大学などの教育・研究機関にも大きな賛同を呼び、2025年2月には東京大学、大阪大学、一橋大学など13の大学が加盟した「共助資本主義の実現に向けた大学連合」(SOLVE!)が結成されました。本学もいつかはその一翼を担いたいと私は考えております。
なぜかというと、その「共助資本主義」の象徴的な事例が、能登半島・石川県地域に出現しているからです。
2024年、元旦「能登半島地震」で奥能登の3つの市町にある11の酒蔵はいずれも大きな被害を受け、昨年の酒造りは絶望的と言われました。ところが、3月から初夏にかけて、いつもとは違う形ですが、新酒が出来上がりました。まさに奇跡です。この奇跡は、金沢市、白山市、小松市、加賀市などの同業酒造会社の皆さんが、県外の長野県や宮城県の酒蔵にも呼び掛け、被災した能登の蔵から日本酒のもととなる「酒米」や「もろみ」を引き取り、協同で製造を代行し、また元に戻し、資金の提供も行って完成させたものでした。
その中の一つ、昨年6月に発売された白山市車多(しゃた)酒造と珠洲市の櫻田酒造の共助を見てみましょう。瓶のラベルには「能登の酒蔵復興応援」と朱書され、「能登大慶×天狗舞」の銘柄表示があります。おまけに豊漁を意味する「大慶」と、大漁を喜んで舞い踊る天狗の姿が青い海の色で印象深く描かれています。左下には小さく製造者として車多酒造の名が記され、その裏側には全壊した櫻田酒造の瓦礫の上に立ち、「新櫻田酒造建設予定地」と段ボールに手書きした看板と櫻田酒造の銘柄「能登初桜」を手に、再建を誓う櫻田博克氏の写真と、協同醸造に至った経緯、利益は櫻田酒造復興に充てられる旨が短く書かれています。私はこのラベルに深い感動を覚えました。
資本主義下近代経営学の世界ではライバル会社の不運はいわば自社のビジネスチャンスとなり、企業合併や買収(M&A)によって企業展開が進行すると考えられています。しかし能登の被災酒造家さんたちをめぐる共助活動はこれとは全く異なる発想・思想のもとに展開されているように見えます。これが「共助資本主義」です。今や能登は壮大な「共助資本主義」の実験場として全国から注目されるところとなっています。
皆さん、私は多くの皆さんが今はまだ何をしたらよいかが分からないけれど、いつか自分たちの手で社会をより良くしたい、と考えておられる方が増えてきていると実感しています。昨年1月、能登半島支援の学生ボランティアを募ったところ、2日間であっという間に135名の学生の皆さんから登録申し込みをいただきました。ありがたく、また尊いことです。皆さんも同様であろうと思います。目の前にある身近な問題から、地球規模の課題に至るまで、見てみぬふりをして背を向けるのではなく、できることから取り組んでまいりましょう。金沢星稜大学では、そのように考え、行動しようとする学生諸君を応援し、様々なプログラムや機会を提供します。
本日は、入学のお祝いを兼ねて、皆さんお一人おひとりに4年間の宿題を課したいと思います。それはこれからの4年間を、「生涯をかけても出会わなければならない人に出会うための準備の4年間にしなさい」ということです。 生涯をかけても出会わなければならない人、それは恋人かと思われた方も多いかもしれません。それも大事なことですが、私の言っているのは「本当の自分」ということです。
本当の自分と出会う、あるいは見つけるためにはどうしたらよいのでしょうか。それには、他者を知ることが不可欠です。学部や学科、勉強する学問の性格、学風によっても考え方や人間性に違いが出てきます。先生や友人、皆そうです。人は皆、他者との触れ合いの中で、この人は自分と違う、自分にはないものを持っていると気づかされます。そこから、他者をコピーするのではなく、参考にしながら、それまでの自分にはなかった新たな自分を描き、自分を超えようとします。
これからの4年間、あなた方一人ひとりが、自分の殻に閉じこもるのではなく、積極的に他者とかかわり、地域に出かけ、自分を表現してみてください。ただし、自分の宣伝や押しつけの必要はありません。
冒頭に大学はジャングルだと申し上げました。本学は多様性に富んださまざまな人間集団であります。あなた方の多感な4年間に、多様な考え方や人間に触れ、自分を高め、本当の自分に出会うことができる契機になるとすれば、それは一生の宝物になります。
結びに、皆さんが、金沢御所町の自然豊かなキャンパス環境で、充実した教育プログラムと先生方の指導、切磋琢磨する仲間たちとともに、将来に向けた様々な力を身につけ、「誠実にして社会に役立つ人間」になるための学びを深められますように。
 浅野川の桜も開き始め…
浅野川の桜も開き始め…