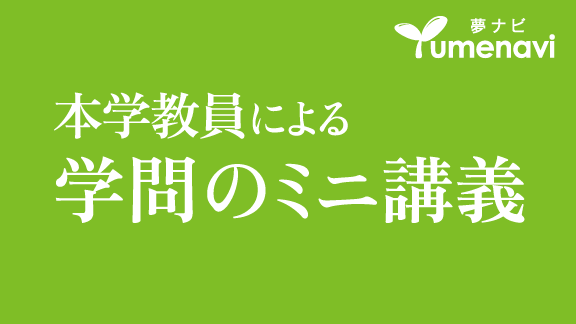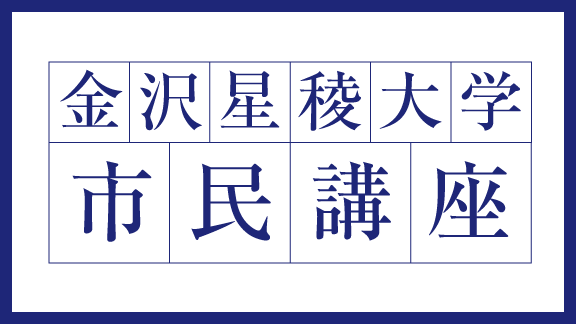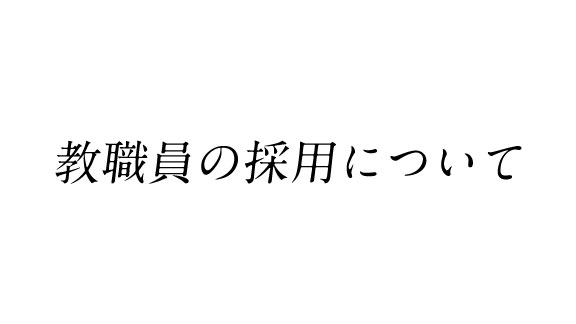学長コラム
「創造する…」
2025.05.01
毎朝散歩する医王の杜公園の10メートルはあろうかと見える巨大なモニュメント「協調」。1980年代後半、金沢大学の角間移転に伴い新しい大学町となった杜の里の発展を祈念したものかと思われます。町内のあちらこちらに展示してある造形物と同様、金沢美大の関係者の作品らしいのですが、詳しくはわかりません。
この「協調」、見上げる毎に思うのは、作者はこれを何の目的で、どうやって作り出したのだろうということ。古代ギリシャに由来する「無から有は生じない」という基本的思想、因果律、つまりものごとには必ず原因があり、しかる後に結果が生じる、逆に言えば結果という現象があるところには須らく原因があるとする考え方が「合理的」とみなされてきました。例えば机一つを作るにしても、大学生が講義室で座って用いる学習用であるとか、もっぱら教員が立って使用する講義用であるとか、どのような目的のために使うのかが分かっていないと机は作れないのです。つまり、一般的にはものには目的が先にあって、然る後にその形や大きさ、あるいは素材がそれに応じて選択され、一つのもの現実態に定まるという順序を踏みます。
「協調」にも、最初に作る目的や意図があり、それに応じて大きさや形が決められ、素材としての大理石やコンクリートなどが材料として選ばれ、加工や組み立ての作用が加わってこのモニュメントとなったということができます。つまり、作者の内には最初から協調のイメージがあったということになります。無から有は生じませんので…。芸術家というのは偉大ですね。
こうした考え方は「合理的」とされ、私たちの身の回りに様々な形で浸透しています。ことに西洋の教育論は基本的にはこの考え方に由来します。教育とは、その人の中に埋もれている才能を表に引き出す「educare, discover」ことでした。だから教えるということは「もともとあった能力」を引き出して増大させるという意味合いになります。
哲学者の内田樹氏が指摘していますが、私たちは、子どもの時から、何かをする時に、何のためにそんなことをするのか、そういう風にするとどんな効果があるのか、という説明があるのが当たり前だと考えています。物を買う時に、商品を手にとって、「これは何の役に立つのか」と尋ねます。そう聞かれて「さあ、よく分かりません。使ってみてください」と答える売り手は普通いませんね。でも私は20年ほど前、植木市で椿の苗木を求めた時、「これはどんな花が咲きますか」と尋ねたところ、「それがよく分からないのですよ。その分安くしておきますから…」と正直に答えてくださった植木屋さんに出会ったことがあります。のちに成長して1つの株から紅白2種類の花を咲かせる珍しい源平椿だったことが分かり、大喜びしたことがあります。
家庭でも学校でも子どもたちは何かをするときに「これをすると、これこれこういう良いことがある」という説明を受けて、取り組み始める。努力に対して、どのような報償があるか予め示されているから人間は努力する。報償が示されなければ、努力する人間などいないというのが、ヨーロッパから伝わった教育論の基本的な視点だというのです。武道家でもある内田氏は、日本の修行論には、「もともと自分の中になかったものを獲得する」。つまり、「無から有が生じる」という考え方を持ち、修業を積み重ねていくと「突然悟りを開く」境地を体験するとことが重要と説いています。これも傾聴すべき論かと思います。
「無から有が生じる」という考え方の最も古くから知られる代表は旧約聖書「創世記」 の「天地創造」でしょう。現在、われわれの身の回りには「未来創造」、「地域創造」、「地域未来創造」など、しばしば創造という語が用いられます。能登半島の「創造的復興論」もそうですね。「創造」とは、一般に新しいものを初めてつくり出すことではあります。
しかしながら元来、創造は旧約聖書「創世記」 の「はじめに神は天と地とを創造された」とされるあの記述に由来します。神が天と地を創造したということは天と地がそこから始まったということです。それ以前にはなく、いきなり神がこの世を作り出したというのです。神には目的や形、材料があらかじめあったのかもしれないが、神ならぬわれわれ人間にはこんなこと、知る由もない。ギリシャ人たちだったら、到底承認できないでしょう。原因がなかったのに結果としての現実態がある、つまり無から有が生じたのですから。「神は死んだ」とするニーチェも同様に「そんなものはそもそも存在しない、まっぴらごめんだ」といったことでしょう。
創造という時に、実はわれわれは誰もその完成形に備わっている目的や形式、本質など予め分かって持っているわけではないのだということを確認しておくべきでしょう。例えば能登の創造的復興をどうしたらよいのか、分かっているようで、実は全体像は誰にも見えない。見えないけれど、いつの日か、自分たちの手でより良くしたい。私たちができることは目の前にある身近な問題から、地球規模の課題に至るまで、見てみぬふりをして背を向けるのではなく、できることから地道に取り組み続けることが重要であるのでしょう。内田氏のように仮に突然悟りが開けることなどなくとも、それはそれでよいのではないでしょうか。
この「協調」、見上げる毎に思うのは、作者はこれを何の目的で、どうやって作り出したのだろうということ。古代ギリシャに由来する「無から有は生じない」という基本的思想、因果律、つまりものごとには必ず原因があり、しかる後に結果が生じる、逆に言えば結果という現象があるところには須らく原因があるとする考え方が「合理的」とみなされてきました。例えば机一つを作るにしても、大学生が講義室で座って用いる学習用であるとか、もっぱら教員が立って使用する講義用であるとか、どのような目的のために使うのかが分かっていないと机は作れないのです。つまり、一般的にはものには目的が先にあって、然る後にその形や大きさ、あるいは素材がそれに応じて選択され、一つのもの現実態に定まるという順序を踏みます。
「協調」にも、最初に作る目的や意図があり、それに応じて大きさや形が決められ、素材としての大理石やコンクリートなどが材料として選ばれ、加工や組み立ての作用が加わってこのモニュメントとなったということができます。つまり、作者の内には最初から協調のイメージがあったということになります。無から有は生じませんので…。芸術家というのは偉大ですね。
こうした考え方は「合理的」とされ、私たちの身の回りに様々な形で浸透しています。ことに西洋の教育論は基本的にはこの考え方に由来します。教育とは、その人の中に埋もれている才能を表に引き出す「educare, discover」ことでした。だから教えるということは「もともとあった能力」を引き出して増大させるという意味合いになります。
哲学者の内田樹氏が指摘していますが、私たちは、子どもの時から、何かをする時に、何のためにそんなことをするのか、そういう風にするとどんな効果があるのか、という説明があるのが当たり前だと考えています。物を買う時に、商品を手にとって、「これは何の役に立つのか」と尋ねます。そう聞かれて「さあ、よく分かりません。使ってみてください」と答える売り手は普通いませんね。でも私は20年ほど前、植木市で椿の苗木を求めた時、「これはどんな花が咲きますか」と尋ねたところ、「それがよく分からないのですよ。その分安くしておきますから…」と正直に答えてくださった植木屋さんに出会ったことがあります。のちに成長して1つの株から紅白2種類の花を咲かせる珍しい源平椿だったことが分かり、大喜びしたことがあります。
家庭でも学校でも子どもたちは何かをするときに「これをすると、これこれこういう良いことがある」という説明を受けて、取り組み始める。努力に対して、どのような報償があるか予め示されているから人間は努力する。報償が示されなければ、努力する人間などいないというのが、ヨーロッパから伝わった教育論の基本的な視点だというのです。武道家でもある内田氏は、日本の修行論には、「もともと自分の中になかったものを獲得する」。つまり、「無から有が生じる」という考え方を持ち、修業を積み重ねていくと「突然悟りを開く」境地を体験するとことが重要と説いています。これも傾聴すべき論かと思います。
「無から有が生じる」という考え方の最も古くから知られる代表は旧約聖書「創世記」 の「天地創造」でしょう。現在、われわれの身の回りには「未来創造」、「地域創造」、「地域未来創造」など、しばしば創造という語が用いられます。能登半島の「創造的復興論」もそうですね。「創造」とは、一般に新しいものを初めてつくり出すことではあります。
しかしながら元来、創造は旧約聖書「創世記」 の「はじめに神は天と地とを創造された」とされるあの記述に由来します。神が天と地を創造したということは天と地がそこから始まったということです。それ以前にはなく、いきなり神がこの世を作り出したというのです。神には目的や形、材料があらかじめあったのかもしれないが、神ならぬわれわれ人間にはこんなこと、知る由もない。ギリシャ人たちだったら、到底承認できないでしょう。原因がなかったのに結果としての現実態がある、つまり無から有が生じたのですから。「神は死んだ」とするニーチェも同様に「そんなものはそもそも存在しない、まっぴらごめんだ」といったことでしょう。
創造という時に、実はわれわれは誰もその完成形に備わっている目的や形式、本質など予め分かって持っているわけではないのだということを確認しておくべきでしょう。例えば能登の創造的復興をどうしたらよいのか、分かっているようで、実は全体像は誰にも見えない。見えないけれど、いつの日か、自分たちの手でより良くしたい。私たちができることは目の前にある身近な問題から、地球規模の課題に至るまで、見てみぬふりをして背を向けるのではなく、できることから地道に取り組み続けることが重要であるのでしょう。内田氏のように仮に突然悟りが開けることなどなくとも、それはそれでよいのではないでしょうか。
 筆者撮影「協調」(医王の杜公園)
筆者撮影「協調」(医王の杜公園)
参考文献
内田樹『修行論』光文社新書、2013
川原栄峰『哲学入門以前』南窓社、1967(第18刷、2003)
内田樹『修行論』光文社新書、2013
川原栄峰『哲学入門以前』南窓社、1967(第18刷、2003)