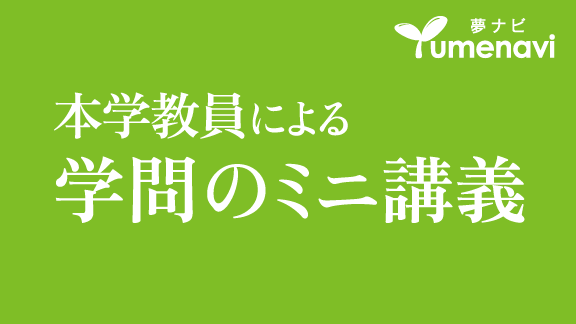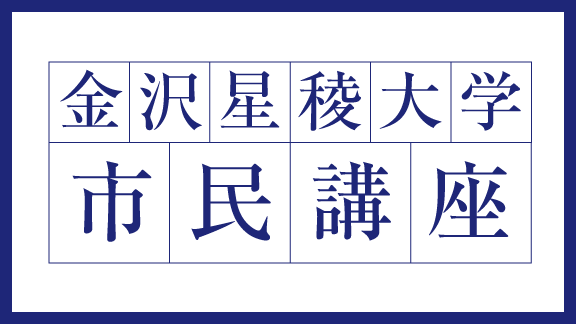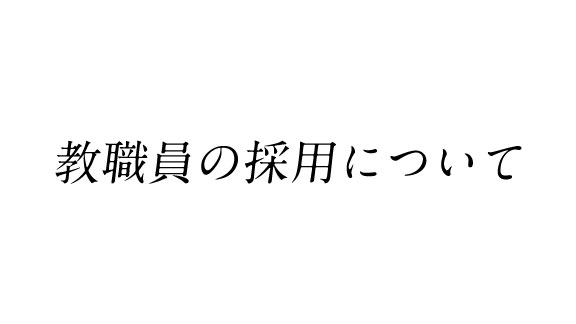学長コラム
「200万年の不条理」
2025.07.01
首都圏に暮らす愚息一家に、つい先日、7歳の女の子、3歳の男の子に続いて、3人目の孫が生まれたとのこと。遠方ゆえ、すぐに駆け付けることもかなわないのですが、情報通信技術が進んだ今日、パソコン画面で簡単に一家の様子を見るのはまことにうれしく、ありがたいことです。ところが3歳になる2番目の孫がおかしくなったと息子の弁。夜中にぐずぐず泣いたり、すねたり、いわゆる「赤ちゃん返り」とのこと。確かに画面で見ても、赤ちゃんにミルクをやったり撫でてあげたり、可愛がってはいるものの、顔の表情や態度には、どこか困ったような、拗ねているような、自分の気持ちを持て余している様子がありあり。
2番目の孫にとっては、出産入院とはいえ、初めてママのいない夜を過ごしたと思ったら、急に赤ちゃんを連れて自宅に戻り、それ以後ママもパパも赤ちゃんにかかりきり、大好きなお姉ちゃんまで赤ちゃんを抱っこしてにこにこしているものですから、「複雑な思い」にとらわれるのは当然なことでしょう。つい先日まで自分が一番幼く、家族の真ん中にいて皆に可愛がってもらっていたのに、いきなりその座を奪われたのですから…。自分は何もしていないのに…、そういう孫の気持ちを察すると、なんだか切なく、たまらなくいとおしくなります。
50年以上も昔の講義。自分には責任がないのに、いきなり世界が、常識に反して不合理に変わることを「不条理」、そうした中で自分がつま弾きされ、必要とされていないという感情を抱くことを、「疎外」と言うのだ、不条理はAbsurdität(アプシュルディテート)、疎外はEntfremdung(エントフレムデゥング)というのだとドイツ語まで教えられ、初めて大学生になった気がして陶酔したことを思い出します。
今、3歳の孫を見ていると、何のことはない。全身で「不条理」に向き合っているではないですか。
保育学の先生にお尋ねしたところ、赤ちゃん返りは、子どもによって個人差はあるものの一般的には一時的な現象であり、期間でいえば数週間から半年程度(平均5.3ヶ月)、4歳ごろには落ち着く事が多いとのことです。つまり「みんな」そうなのです。人類の起源であるヒト属はおよそ200万年前にアフリカでアウストラロピテクス属から分化したとされますから、200万年前から人は同じことを繰り返してきたのでしょう。
高校の時に学んだ『伊勢物語』「東下り」。「昔、男ありけり。その男、身をえうなきものに思ひなして、京にはあらじ、東の方に住むべき国求めにとて行きけり」との書き出しを読んで、驚き、感動したことを思い出します。「千年前にわが身がこの世に無用な存在ではないか、どこに住むべき国があるのだろうと、自分と同じことを考えた人がいる! 」
その思いは通奏低音のように大学生になっても続いていたのですが、マックス・ヴェーバーだったと思いますが、“ein Mensch unter den Menschen ”「数多の人間の中の一人」という言葉を知り、200万年前から、すべての人間は生まれ、生き、皆死んでいった。自分もその普遍(理)の中に淡々と身を投ずればよいのだと思うに至って、初めて落ち着いて勉学に取り組み、生きていけるようになったと今になって思い起こします。若い時分には死への恐怖や不安も大きかったのですが、75歳を過ぎたこの年になるともうそうではありません。200万年前から、誰一人死ななかった人はいないのですから。私にもできないはずがありません。
じじバカの話から、「不条理」ということについて考えてきました。2024年の「能登半島地震」はまさに不条理でしたが、その復興に不条理があってはなりません。本学の皆さんの地道ですが、活発で積極的な復興支援やボランティア活動に感謝と敬意を表します。あの日から1年と6か月目の7月1日です。 (なお次回の学長コラムは9月1日予定です。)
2番目の孫にとっては、出産入院とはいえ、初めてママのいない夜を過ごしたと思ったら、急に赤ちゃんを連れて自宅に戻り、それ以後ママもパパも赤ちゃんにかかりきり、大好きなお姉ちゃんまで赤ちゃんを抱っこしてにこにこしているものですから、「複雑な思い」にとらわれるのは当然なことでしょう。つい先日まで自分が一番幼く、家族の真ん中にいて皆に可愛がってもらっていたのに、いきなりその座を奪われたのですから…。自分は何もしていないのに…、そういう孫の気持ちを察すると、なんだか切なく、たまらなくいとおしくなります。
50年以上も昔の講義。自分には責任がないのに、いきなり世界が、常識に反して不合理に変わることを「不条理」、そうした中で自分がつま弾きされ、必要とされていないという感情を抱くことを、「疎外」と言うのだ、不条理はAbsurdität(アプシュルディテート)、疎外はEntfremdung(エントフレムデゥング)というのだとドイツ語まで教えられ、初めて大学生になった気がして陶酔したことを思い出します。
今、3歳の孫を見ていると、何のことはない。全身で「不条理」に向き合っているではないですか。
保育学の先生にお尋ねしたところ、赤ちゃん返りは、子どもによって個人差はあるものの一般的には一時的な現象であり、期間でいえば数週間から半年程度(平均5.3ヶ月)、4歳ごろには落ち着く事が多いとのことです。つまり「みんな」そうなのです。人類の起源であるヒト属はおよそ200万年前にアフリカでアウストラロピテクス属から分化したとされますから、200万年前から人は同じことを繰り返してきたのでしょう。
高校の時に学んだ『伊勢物語』「東下り」。「昔、男ありけり。その男、身をえうなきものに思ひなして、京にはあらじ、東の方に住むべき国求めにとて行きけり」との書き出しを読んで、驚き、感動したことを思い出します。「千年前にわが身がこの世に無用な存在ではないか、どこに住むべき国があるのだろうと、自分と同じことを考えた人がいる! 」
その思いは通奏低音のように大学生になっても続いていたのですが、マックス・ヴェーバーだったと思いますが、“ein Mensch unter den Menschen ”「数多の人間の中の一人」という言葉を知り、200万年前から、すべての人間は生まれ、生き、皆死んでいった。自分もその普遍(理)の中に淡々と身を投ずればよいのだと思うに至って、初めて落ち着いて勉学に取り組み、生きていけるようになったと今になって思い起こします。若い時分には死への恐怖や不安も大きかったのですが、75歳を過ぎたこの年になるともうそうではありません。200万年前から、誰一人死ななかった人はいないのですから。私にもできないはずがありません。
じじバカの話から、「不条理」ということについて考えてきました。2024年の「能登半島地震」はまさに不条理でしたが、その復興に不条理があってはなりません。本学の皆さんの地道ですが、活発で積極的な復興支援やボランティア活動に感謝と敬意を表します。あの日から1年と6か月目の7月1日です。 (なお次回の学長コラムは9月1日予定です。)
 筆者撮影「あじさい」
筆者撮影「あじさい」