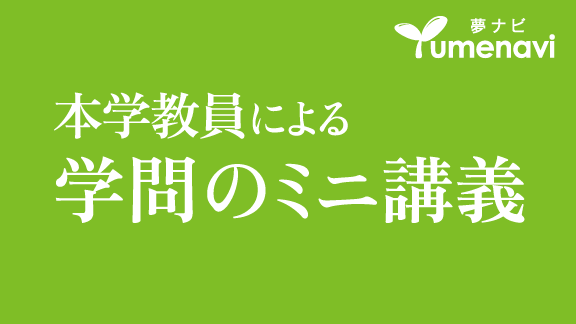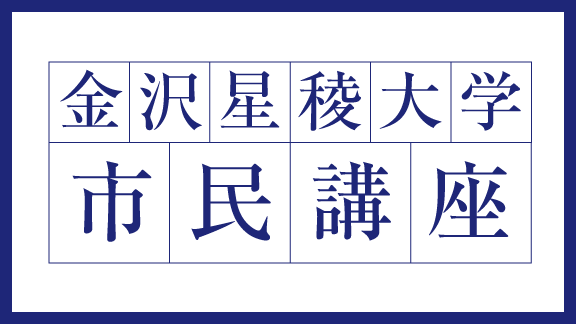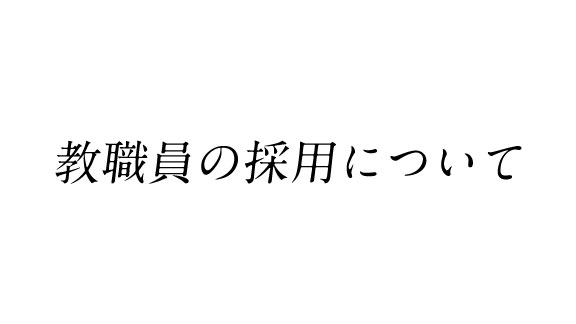学長コラム
「ほし☆たび北海道2025」に贈る言葉
2025.09.01
金沢星稜大学・同女子短大部進路支援課が主催する名物洋上就職合宿クルーズ、3泊4日「ほし☆たび北海道2025」が間もなく出発。先日、キックオフ結団式に出席しました。
今年は、57名の大学1~2年次・短大1年次クルーに、スキッパー9名(就職を納得の結果で終えた4年次)、職員ほか総勢72名の参加。名古屋港から太平洋フェリーに乗り込み、苫小牧西港まで2泊、40時間のクルーズ。この間、寄港する仙台付近を除けば、20~30㎞の沖合を航行するため、陸地は見えてもスマホの電波は届きません。大型フェリーとはいえ、船内には逃げ場もなく、ひたすら、「プレゼンテーション」「グループ・ディスカッション」「ロジカル・シンキング」など、先輩スキッパーの体験とアドバイスをもとにして、自己分析や面接対策の手法などを真剣勝負で繰り返します。フェリーでの濃密な研修を終えてからも、札幌市郊外の研修施設に移動して、さらに仕上げの1泊。最終日は札幌駅前で解散、帰りの行程は自分で自由に計画し、実行せよという、怒涛の就職対策合宿です。
このような本格的な就職活動とは全く無縁な大学生活を送った私は、当初「ほし☆たび北海道」は、面接時のノウハウを中心とした過剰なまでの「就職活動支援サービス」ではないかとの印象を持っていたのですが、何度か同行参加して、これは金沢星稜大学における「隠れたカリキュラム The Hidden Curriculum」だと気づかされました。「隠れたカリキュラム」とは、公式なカリキュラムの中にはない、知識、行動 の様式や性向、意識やメンタリティが、意図しないままに修得されていくことです。
それはおそらく「ほし☆たび北海道」のメインテーマに「ジブンを超えよう」が設定されていることに起因します。サブタイトルは、①他者と関わり、ジブンを知る、②相手の心に届くプレゼンテーション、③就職活動を終えた先輩の強みを知る、の3つ。つまり、実践的なプログラムを通し、最終的なゴールは「ジブンを超える」と哲学的に設定されています。
このようなことからキックオフ結団式で、サルトル『存在と無』(注1)を例に引き、私は次のように激励しました。
自分を振り返る時、「即自存在」、「対他存在」、「対自存在」という3段階のレベルがあります。「即自存在」というのは、例えれば動物そのものの私(腹が減ったから食べる、食べたら眠る)。「対他存在」というのは他者の眼を通して見える私。(あの人はこんなに頑張っている、それに比べて私は…と落ち込む場合がこれ)。「ほし☆たび北海道」は「他者と関わり、ジブンを知る」と掲げてあるように、多くのプログラムは「対他存在」としての自己認識を強化して「ジブンを超える」ことにつなげようとする研修。でももう一つ、人間には「対自存在」があります。他者に憧れ、目標にして、それに近づけようとする「対他存在」に対して、本当の自分とは何だろうと自分で自分自身に向き合おうとすることです。
「わたしは、わたしを相手に、いつも対話に熱中しすぎる。…第三者は、二人の対話が深みに沈み込むのを阻止するコルク製の浮子(うき)なのだ。」(注2)ニーチェはこう言って自分で自分に向き合うことの重要性を述べます。
電波の届かないスマホはちょうどコルク製の浮子。船上の数時間に過ぎないかもしれませんが、バッグの奥にしまい込んで、ジブンとの対話に沈み込んでみませんか。若者にとって自身の才能や知識など本当の自分をさらけ出すことはとても困難で辛いことです。ついつい自己を韜晦(とうかい:包み隠すこと)しがちですが、「ジブンを超えよう」とするあなたにとって「ほし☆たび北海道」は韜晦を脱ぎ捨てる「得難い経験と時間になることでしょう。ボン・ボヤージュ(bon voyage!)
今年は、57名の大学1~2年次・短大1年次クルーに、スキッパー9名(就職を納得の結果で終えた4年次)、職員ほか総勢72名の参加。名古屋港から太平洋フェリーに乗り込み、苫小牧西港まで2泊、40時間のクルーズ。この間、寄港する仙台付近を除けば、20~30㎞の沖合を航行するため、陸地は見えてもスマホの電波は届きません。大型フェリーとはいえ、船内には逃げ場もなく、ひたすら、「プレゼンテーション」「グループ・ディスカッション」「ロジカル・シンキング」など、先輩スキッパーの体験とアドバイスをもとにして、自己分析や面接対策の手法などを真剣勝負で繰り返します。フェリーでの濃密な研修を終えてからも、札幌市郊外の研修施設に移動して、さらに仕上げの1泊。最終日は札幌駅前で解散、帰りの行程は自分で自由に計画し、実行せよという、怒涛の就職対策合宿です。
このような本格的な就職活動とは全く無縁な大学生活を送った私は、当初「ほし☆たび北海道」は、面接時のノウハウを中心とした過剰なまでの「就職活動支援サービス」ではないかとの印象を持っていたのですが、何度か同行参加して、これは金沢星稜大学における「隠れたカリキュラム The Hidden Curriculum」だと気づかされました。「隠れたカリキュラム」とは、公式なカリキュラムの中にはない、知識、行動 の様式や性向、意識やメンタリティが、意図しないままに修得されていくことです。
それはおそらく「ほし☆たび北海道」のメインテーマに「ジブンを超えよう」が設定されていることに起因します。サブタイトルは、①他者と関わり、ジブンを知る、②相手の心に届くプレゼンテーション、③就職活動を終えた先輩の強みを知る、の3つ。つまり、実践的なプログラムを通し、最終的なゴールは「ジブンを超える」と哲学的に設定されています。
このようなことからキックオフ結団式で、サルトル『存在と無』(注1)を例に引き、私は次のように激励しました。
自分を振り返る時、「即自存在」、「対他存在」、「対自存在」という3段階のレベルがあります。「即自存在」というのは、例えれば動物そのものの私(腹が減ったから食べる、食べたら眠る)。「対他存在」というのは他者の眼を通して見える私。(あの人はこんなに頑張っている、それに比べて私は…と落ち込む場合がこれ)。「ほし☆たび北海道」は「他者と関わり、ジブンを知る」と掲げてあるように、多くのプログラムは「対他存在」としての自己認識を強化して「ジブンを超える」ことにつなげようとする研修。でももう一つ、人間には「対自存在」があります。他者に憧れ、目標にして、それに近づけようとする「対他存在」に対して、本当の自分とは何だろうと自分で自分自身に向き合おうとすることです。
「わたしは、わたしを相手に、いつも対話に熱中しすぎる。…第三者は、二人の対話が深みに沈み込むのを阻止するコルク製の浮子(うき)なのだ。」(注2)ニーチェはこう言って自分で自分に向き合うことの重要性を述べます。
電波の届かないスマホはちょうどコルク製の浮子。船上の数時間に過ぎないかもしれませんが、バッグの奥にしまい込んで、ジブンとの対話に沈み込んでみませんか。若者にとって自身の才能や知識など本当の自分をさらけ出すことはとても困難で辛いことです。ついつい自己を韜晦(とうかい:包み隠すこと)しがちですが、「ジブンを超えよう」とするあなたにとって「ほし☆たび北海道」は韜晦を脱ぎ捨てる「得難い経験と時間になることでしょう。ボン・ボヤージュ(bon voyage!)
注1)サルトル(松浪信三郎訳)『存在と無』Ⅰ、ちくま学芸文庫、2007
注2)ニーチェ(吉沢伝三郎訳)『このようにツァラトゥストラは語った』(上)、講談社文庫、1971、112頁「友人について」
注2)ニーチェ(吉沢伝三郎訳)『このようにツァラトゥストラは語った』(上)、講談社文庫、1971、112頁「友人について」
 筆者撮影「涼のきらめき」(卯辰山)
筆者撮影「涼のきらめき」(卯辰山)