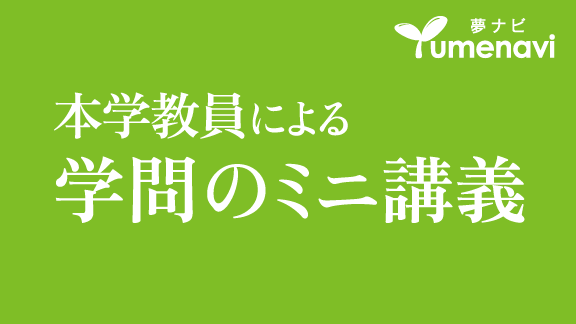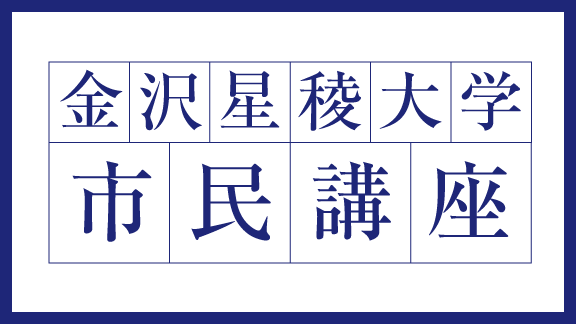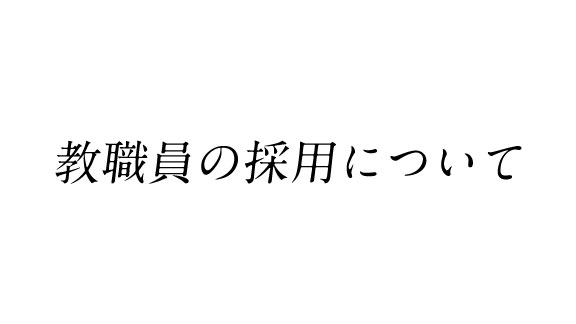学長コラム
「明治期の生徒作文と運動会」
2025.10.01
10月は各学校の運動会が行われる季節。この運動会、わが国独自の学校文化と言われ、その成立を巡る歴史的な研究も個別事実史、思想史的研究のほか、社会史的研究も蓄積されてきています。総じてこれらの研究には、新聞や教育会雑誌、主催した学校や行政関係者側の実施記録などが主史料として用いられることが多かったことは否めません。
そうした中で、2000年、石川県立歴史博物館に「明治期金沢市内小学生作文」(資料番号2-18-2006)が収蔵されたと、本康宏史氏(当時学芸員、現金沢星稜大学特任教授)から教えていただきました。金沢市内小学生63名が毛筆やペンで書いた全部で200編余の作文です。作文の全体概要、寄贈者の東京在住上杉緑氏等については、本康氏が既に論文をお書きになっておられますので、興味のある方はそちらをご覧いただくことにしましょう。
私はこの本康論文に触発されながら、全部で13編の「金沢市小学校連合運動会」作文に目を通しました。運動会に参加した生徒の作文というからには、勝敗に一喜一憂する姿はもちろんのこと、筋肉の軋み、はては汗の匂いなど生徒たちの心情の発露や想いが何らかの形で綴られているのではないかとの期待です。これまでとは違った生徒側の視点から運動会を見ることができるのではないか。ところがそうは問屋が卸しませんでした。例えば次の作文を見てみましょう。
扇沢啓吉 「金沢市内各小学校連合運動会の記」
明治31年10月10日、金沢市内各小学校連合運動会を出羽町練兵場において開く。この日は天気晴朗にして一点の雲なし。余輩大いに喜び、勇壮なる服装をなし、7時頃学校に出づ。これより隊を組みて練兵場に至る。練兵場には2か所に満艦飾を模したる旗を立てられたり。その一つは高岡町高等小学校のものにして、他の一つは本校のものなり。午前10時を以って開会せり。尋常(小学校:筆者)のことは見るを得ざりしゆえ、ここには掲げず。はじめは本校1学年の「一人一脚競走」3回、次に3学年の「旗手乗り換え旗取り競走」2回。次に第2学年の「途中馬乗り換え旗取り競走」3回。次に高岡町1学年生徒の「梅鉢」2回、次に本校全生徒整列して「君が代」の唱歌を2回合唱し、並びに分列式を行う。次に本校第3第4学年の大隊運動をなし、これより飯を食して後、高岡町第2学年の「汽車」2回、次に本校第1学年の「二人三脚競走」3回、次に高岡町第3・4学年の「鞆(とも)絵」2回、次に本校4学年の「障害物競走」4回、次に同4学年の「中隊運動」。次に本校1学年の「虎穴に入らずば」の軍歌合唱、次に本校全生徒「黄海の大勝」の軍歌合唱し、これよりその場を退き、元長谷川家の跡にて田所校長様よりお話を聞き、これよりその場にて解散し、各家に帰れば時まさに4時頃なりき。(句読点、一部現代漢字、送りひらがな:筆者)
他の運動会作文も大同小異です。あまりにもパターン化しています。これには何かお手本があったのではないかと推測し、運動会が実施された翌日の『北國新聞』(明治31年10月11日)を見ると、二段抜きで「運動会の景況」が詳しく網羅的に報じられており、その時系列的な事実報道の書き方が酷似していることが判明しました。また練兵場に立てられた旗は、「金沢高等小学校、高岡町高等小学校の製作」と明記されていることから、扇沢啓吉は金沢高等小学校の生徒であったことになります。つまり、北國新聞の記事を本として、その中の一部に着目し、自分の視点を若干補足するなどして、金沢市内生徒作文が書かれたことになります。
教育史や体育史の世界では、とかく教える側からの制度史、思想史になりがちで、「生徒の顔が見える歴史を!」と言われてきました。生徒作文はその壁を突破する一手段になるのではないかと安易に期待した私には大変残念な結果となりました。と同時に苦い教訓となりました。国語教育史に詳しい先生にお聞きしたところ、自分の生活や思いを自由に綴るようになったのは、1920~30年代の「生活綴り方運動」以後のことで、それまでは基本お手本をまねるのが作文教育であったとか。
翻って考えてみると、現在の私たちは本当に自由にものを考えたり、発言したりしているのでしょうか?新聞やテレビ、あるいはSNS上で言われるインフルエンサーの意見や見方考え方をそのまま借りていることはないのでしょうか。自分では気づかないままに。
そうした中で、2000年、石川県立歴史博物館に「明治期金沢市内小学生作文」(資料番号2-18-2006)が収蔵されたと、本康宏史氏(当時学芸員、現金沢星稜大学特任教授)から教えていただきました。金沢市内小学生63名が毛筆やペンで書いた全部で200編余の作文です。作文の全体概要、寄贈者の東京在住上杉緑氏等については、本康氏が既に論文をお書きになっておられますので、興味のある方はそちらをご覧いただくことにしましょう。
私はこの本康論文に触発されながら、全部で13編の「金沢市小学校連合運動会」作文に目を通しました。運動会に参加した生徒の作文というからには、勝敗に一喜一憂する姿はもちろんのこと、筋肉の軋み、はては汗の匂いなど生徒たちの心情の発露や想いが何らかの形で綴られているのではないかとの期待です。これまでとは違った生徒側の視点から運動会を見ることができるのではないか。ところがそうは問屋が卸しませんでした。例えば次の作文を見てみましょう。
扇沢啓吉 「金沢市内各小学校連合運動会の記」
明治31年10月10日、金沢市内各小学校連合運動会を出羽町練兵場において開く。この日は天気晴朗にして一点の雲なし。余輩大いに喜び、勇壮なる服装をなし、7時頃学校に出づ。これより隊を組みて練兵場に至る。練兵場には2か所に満艦飾を模したる旗を立てられたり。その一つは高岡町高等小学校のものにして、他の一つは本校のものなり。午前10時を以って開会せり。尋常(小学校:筆者)のことは見るを得ざりしゆえ、ここには掲げず。はじめは本校1学年の「一人一脚競走」3回、次に3学年の「旗手乗り換え旗取り競走」2回。次に第2学年の「途中馬乗り換え旗取り競走」3回。次に高岡町1学年生徒の「梅鉢」2回、次に本校全生徒整列して「君が代」の唱歌を2回合唱し、並びに分列式を行う。次に本校第3第4学年の大隊運動をなし、これより飯を食して後、高岡町第2学年の「汽車」2回、次に本校第1学年の「二人三脚競走」3回、次に高岡町第3・4学年の「鞆(とも)絵」2回、次に本校4学年の「障害物競走」4回、次に同4学年の「中隊運動」。次に本校1学年の「虎穴に入らずば」の軍歌合唱、次に本校全生徒「黄海の大勝」の軍歌合唱し、これよりその場を退き、元長谷川家の跡にて田所校長様よりお話を聞き、これよりその場にて解散し、各家に帰れば時まさに4時頃なりき。(句読点、一部現代漢字、送りひらがな:筆者)
他の運動会作文も大同小異です。あまりにもパターン化しています。これには何かお手本があったのではないかと推測し、運動会が実施された翌日の『北國新聞』(明治31年10月11日)を見ると、二段抜きで「運動会の景況」が詳しく網羅的に報じられており、その時系列的な事実報道の書き方が酷似していることが判明しました。また練兵場に立てられた旗は、「金沢高等小学校、高岡町高等小学校の製作」と明記されていることから、扇沢啓吉は金沢高等小学校の生徒であったことになります。つまり、北國新聞の記事を本として、その中の一部に着目し、自分の視点を若干補足するなどして、金沢市内生徒作文が書かれたことになります。
教育史や体育史の世界では、とかく教える側からの制度史、思想史になりがちで、「生徒の顔が見える歴史を!」と言われてきました。生徒作文はその壁を突破する一手段になるのではないかと安易に期待した私には大変残念な結果となりました。と同時に苦い教訓となりました。国語教育史に詳しい先生にお聞きしたところ、自分の生活や思いを自由に綴るようになったのは、1920~30年代の「生活綴り方運動」以後のことで、それまでは基本お手本をまねるのが作文教育であったとか。
翻って考えてみると、現在の私たちは本当に自由にものを考えたり、発言したりしているのでしょうか?新聞やテレビ、あるいはSNS上で言われるインフルエンサーの意見や見方考え方をそのまま借りていることはないのでしょうか。自分では気づかないままに。
参考文献
本康宏史「作文に見る明治30年代の招魂祭」『石川県立歴史博物館紀要』17号、2005、127-145頁
大久保英哲「生徒作文に書かれた明治30年代の運動会:明治期金沢市内生徒作文から」、山本徳郎ほか『多様な身体への目覚め:身体訓練の歴史に学ぶ』アイオーエム、2006、154-180頁
本康宏史「作文に見る明治30年代の招魂祭」『石川県立歴史博物館紀要』17号、2005、127-145頁
大久保英哲「生徒作文に書かれた明治30年代の運動会:明治期金沢市内生徒作文から」、山本徳郎ほか『多様な身体への目覚め:身体訓練の歴史に学ぶ』アイオーエム、2006、154-180頁
 筆者撮影「浅野川の彼岸花」
筆者撮影「浅野川の彼岸花」