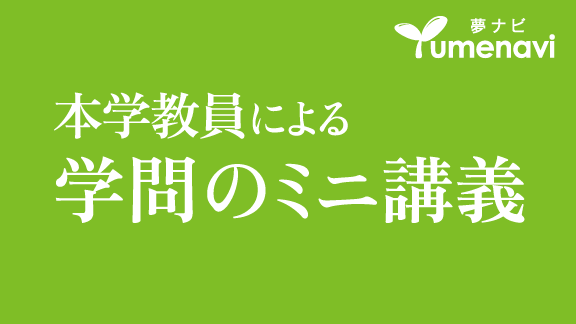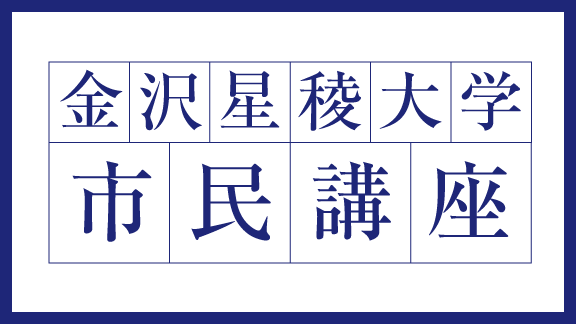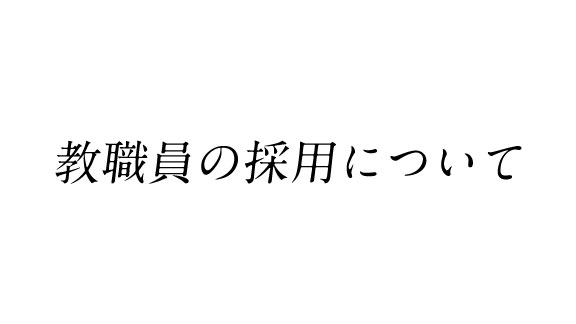人間科学研究2
人間科学研究2
第19巻第1号 (2025年9月発行)
| 1 | ボルネオの熱帯雨林と私たちの暮らし | 中西 宣夫・三好 伸子 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 絵本『ねんねこ ねんねこ ピー』が促す保育者の対話と省察 ─午睡支援における集合的保育力の醸成─ | 三好 伸子・谷 昌代 | 7 |
| 3 | 台湾に対する日本の大学生の認識の変化 ─台湾の小学生と直接交流をした大学生のアンケート調査を通して─ | 清水 和久 | 19 |
| 4 | 幼保小接続に関する一考察 ─保育の歌と小学校音楽科の歌─ | 直江 学美 | 29 |
| 5 | 握力における活動後増強の効果 ─利き手,性別,競技特性に着目して─ | 水越 悠太・塩田 耕平 | 35 |
| 6 | 2024年度人間科学部卒業研究優秀賞報告書要旨 | 柳川 公三子 | 43 |
| 7 | 編集後記 | 永坂 正夫 |
第18巻第2号 (2025年3月発行)
| 1 | 加賀藩校から近代学校へ ─近代黎明期の「金沢中学校」の教育を担った教師は誰か─ | 井上 好人 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 大学体育における生成AIを用いた協働的学習の効果に関する実践研究 ─コミュニケーション能力への影響に着目して─ | 島倉 晴信・丸井 一誠・森永 秀典 | 9 |
| 3 | HMDを活用した小学校での授業実践 ─小学校英語における道案内の授業を通して─ | 清水 和久 | 15 |
| 4 | アドルフォ・サルコリの音楽活動に関する研究(11) ─シチリアにおける演奏活動─ | 直江 学美 | 21 |
| 5 | 描き動かすプログラミング表現活動の可能性 ─保育内容人間関係の授業感想からの考察─ | 細谷 貴章・三好 伸子 | 29 |
| 6 | 幼児期における体格と走跳の運動能力との関係性 | 井川 貴裕 | 37 |
| 7 | GI pill 飲用の至適タイミングの検討 | 奥田 鉄人・藤森 拓未 | 43 |
| 8 | スプリントドリル導入が盗塁局面にもたらす効果 ─ Ⅰ県立KS高等学校野球部を対象に─ | 物部 将大 | 47 |
| 9 | 編集後記 | 馬場 治 |
第18巻第1号 (2024年9月発行)
| 1 | ニュージーランド保育実践と乳幼児の記録 ─個人の学びの旅を可視化するラーニング・ストーリーの効果とは─ | 谷島 直樹・三好 伸子 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 教育系学生に対するVR体験とVRコンテンツ教材作成体験の在り方 ─STYLYを使ったVRコンテンツ教材作成実践をとおして─ | 清水 和久 | 7 |
| 3 | (実践報告)こども学科における初年次教育の取り組み ─保幼小連携に着目して─ | 直江 学美・森永 秀典・三好 伸子・佐藤 静恵・島倉 晴信・福田 美月 | 13 |
| 4 | 令和6年能登半島地震と風流 ─青柏祭の事例─ | 大森 重宜 | 23 |
| 5 | テクノロジーと教師のモチベーション ─テクノロジーが日本のEFL教育における教師に与える影響─ | ムーア ホーリー・リンチ ギャビン | 31 |
| 6 | 卒業研究優秀賞報告要旨 | 芥川 元喜・柳川 公三子 | 37 |
| 7 | 編集後記 | 馬場 治 |
第17巻第2号 (2024年3月発行)
| 1 | 教育史研究における学籍データ分析の可能性 ─ 旧制石川県立金沢第一中学校の事例 ─ | 井上 好人 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 児童福祉司は他領域で専門性をどのように発揮していくか ─ 経験者らの実践に着目して ─ | 川並 利治・三和 直人・井上 景・池田 貴昭 | 15 |
| 3 | 台湾との国際協働学習のサポートの在り方─ オンラインコミュニケーションスキルの育成と台湾訪問の経験を通して ─ | 清水 和久 | 25 |
| 4 | ドローン空撮画像を利用した石川県能美市の根上海岸の漂着ごみ分布と清掃活動の評価 | 永坂 正夫・牧野 耀・山本 輝太郎・岸本 秀一 | 33 |
| 5 | 宣命体における否定辞の漢字─ 表意と表音の措辞 ─ | 馬場 治 | 72 |
| 6 | 大学野球選手の足関節捻挫後遺症に対するトレーニング効果について | 杉本 佳幸・杉本 直希・奥田 鉄人 | 39 |
| 7 | 地域食材を題材とした児童向け調理活動の試論─ 小学校「家庭科」を生かす実践事例を中心に ─ | 手塚 貴子 | 45 |
| 8 | 短大生と高校生の「交流作文」における一形態─ クラウド上で行う「交流メール」の可能性 ─ | 山田 範子 | 53 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第17巻第1号 (2023年9月発行)
| 1 | 文部科学省の教育ビジョンを読み解く─ 学制150年,現代の教育改革はどこへ向かうか ─ | 青木 栄一 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 国際協働学習における主体的オンラインコミュニケーションスキルの育成 | 清水 和久・絈野 理子 | 11 |
| 3 | 週1回程度の筋力トレーニングが男子大学生の身体組成,筋力,跳躍能力に及ぼす影響 | 岡室 憲明・物部 将大 | 17 |
| 4 | スポーツ総合演習がスポーツ学科の学生に与える影響について | 中井 玲奈・西村 貴之・島田 一志 | 23 |
| 5 | 多言語・多文化な社会におけるボランティアの可能性 | リンチ ギャビン | 31 |
| 6 | 卒業研究優秀賞報告要旨 | 馬場 治 | 37 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第16巻第2号 (2023年3月発行)
| 1 | 芥川 元喜 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 井上 好人 | 9 | |
| 3 | 三和 直人・川並 利治 | 21 | |
| 4 | 清水 和久 | 33 | |
| 5 | 直江 学美 | 41 | |
| 6 | 馬場 治 | 73 | |
| 7 | 幼大連携による4歳児を対象としたリトミック活動に関する実践報告 ─ 稲置学園創立90周年記念事業“夢のステージ”に向けた取り組み ─ | 連 桃季恵 | 49 |
| 8 | ICTを活用した学生の家庭科授業づくりの一考察 | 手塚 貴子・天野 佐知子 | 57 |
| 9 | 国語教育における「交流作文」の価値─ 短大生と中学生の実践に即して ─ | 山田 範子 | 63 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第16巻第1号 (2022年9月発行)
| 1 | 福祉行政のスーパービジョンから考察する児童相談所スーパーバイザーの特性 | 川並 利治・三宅 右久・三和 直人 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 日常とは異なる視点で撮影可能な機器の活用法─ ドローンカメラ,360度カメラ,VRヘッドセットの活用事例 ─ | 清水 和久 | 11 |
| 3 | アドルフォ・サルコリの音楽活動に関する研究(9)─ デビューに関する記事より ─ | 直江 学美 | 17 |
| 4 | ICT活用の授業におけるピア・フィードバックの手法を活用したペア学習の効果─ 学生のペア学習に対する思考態度の醸成を土台にして ─ | 細川 都司恵 | 23 |
| 5 | 保育者が子どもに触れることの意味─ 午睡場面のかかわりに関する保育所保育指針の整理から ─ | 三好 伸子・荒木 実代 | 29 |
| 6 | 音楽に関する保育実習指導案作成における指導の現状と課題 | 連 桃季恵・三好 伸子 | 37 |
| 7 | 保健体育科教員志望学生の体育授業に対する意識の分析 | 泉 翔王・櫻井 貴志 | 45 |
| 8 | コロナ禍の風流─ 青柏祭の曳山行事の事例 ─ | 大森 重宜・櫻井 貴司・田島 良輝 | 53 |
| 9 | ストレス/リカバリー評価を活用した選手への心理サポート及び連携サポート | 門岡 晋 | 65 |
| 10 | 卒業研究優秀賞報告要旨 | 馬場 治 | 73 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第15巻第2号 (2022年3月発行)
| 1 | 自己リフレクションと対話リフレクションを組み合わせたリフレクション・プログラムの提案─ 学校インターンシップ活動当初をどう支援するのか ─ | 芥川 元喜 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 石川県立高等女学校生徒の「弓術」事始め─ 誰が優等賞を勝ち得たのか ─ | 井上 好人 | 9 |
| 3 | 中核市児童相談所における心理職の確保とキャリアアップに関する考察 | 三宅 右久・川並 利治 | 23 |
| 4 | 国際協働学習における協働性を視点とした学び─ TEDDY BEAR Project を通して ─ | 清水 和久 | 29 |
| 5 | 国語科における伝統的な言語文化の理解と表現─ 俳句の鑑賞と創作を中心に ─ | 馬場 治 | 84 |
| 6 | 保育理解のための動画コンテンツの分析 | 開 仁志 | 37 |
| 7 | タブレット端末を活用した授業における,ペア・小集団学習による対話の取り入れ方についての考察─ 先行研究を整理することを通して ─ | 細川 都司恵 | 45 |
| 8 | 2021年度「健康科学演習」受講者における体力の特徴 | 岡室 憲明・山木 智恵子 | 51 |
| 9 | GI pillを用いた運動時における深部体温の測定 | 奥田 鉄人・宇田 知史・安田 光太郎 | 55 |
| 10 | プロスポーツ観戦者の再観戦意図に与える影響─ 観戦者のサービス・プロダクト評価に着目して ─ | 鳥山 稔・田島 良輝・西村 貴之・佐々木 達也・神野 賢治・池田 幸應 | 63 |
| 11 | 国内トップスイマーと地方ジュニアスイマーの平泳ぎにおけるレース分析比較 | 南部 奏太・奥田 鉄人 | 69 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第15巻第1号 (2021年9月発行)
| 1 | 新学習指導要領に基づく国語科教育とその課題 | 折川 司 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 小特集:新学習指導要領と国語科教育のゆくえ─ 幼小中高大を通じて ─ | 馬場 治・芥川 元喜・森永 秀典・天野 佐知子・山田 範子 | 11 |
| 3 | 中核市児童相談所における療育手帳業務に係る取組と課題 | 三宅 右久・川並 利治 | 29 |
| 4 | 小学校英語を教える学生に必要な英語基礎の内容の考察─ 英語の必要感の持たせ方とスキルアップの手立て ─ | 清水 和久 | 35 |
| 5 | コロナ禍の遠隔授業と学内演習による保育実習の報告 | 三好 伸子・連 桃季恵 | 41 |
| 6 | コロナ禍と風流 | 大森 重宜・田島 良輝 | 51 |
| 7 | 限局性学習障害児に対してタブレットPC(iPad)を支援機器として使った小グループ指導─ 児童用コンピテンス尺度による1年間の指導効果の評価 ─ | 河野 俊寛・山田 彩加・高塚 真緒・堀内 萌・平谷 美智夫 | 59 |
| 8 | 中年者を対象とした遠隔運動教室の事例的研究 | 二ノ宮 健太・前田 有美・齊藤 陽子 | 69 |
| 9 | プロスポーツチームによる地域愛着に地元メディアが与える影響─ 2004年,北海道新聞は北海道日本ハムファイターズをどう伝えたのか ─ | 田島 良輝・藤原 真由美・鳥山 稔・西村 貴之・佐々木 達也・池田 幸應 | 75 |
| 10 | Assets Rediscovered with Foreign Involvement─ Japan’s Hidden Treasures ─ | リンチ ギャビン | 83 |
| 11 | 第2回石川国体(1947)に関する研究(その3)─ 市民が目にした国体都市金沢の風景 ─ | 大久保 英哲 | 89 |
| 12 | 卒業研究優秀賞報告要旨 | 馬場 治 | 99 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第14巻第2号 (2021年3月発行)
| 1 | 学校インターンシップにおける大学生のリフレクションの研究─ リフレクションシートと対話リフレクションを活用した事例 ─ | 芥川 元喜 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 明治期における石川県立高等女学校の「運動会」─ 校友会活動からみた女子体育と身体表現 ─ | 井上 好人 | 9 |
| 3 | 子ども虐待を人任せにしない新たな児童相談所の相談体制の一元化及びスマート化に関する考察 | 川並 利治 | 23 |
| 4 | プログラミング教育のためのワークショップ授業の開発─ 小学生と幼稚園児に対する試行授業を通して ─ | 清水 和久 | 31 |
| 5 | 小学校国語科における「ことわざ」の理解と使用 ─ 表現と意味の関係を中心に ─ | 馬場 治 | 80 |
| 6 | 保育者の研修体系構築に関する一考察─ 法定研修を中心に ─ | 開 仁志 | 39 |
| 7 | COVID-19感染拡大による自粛期間中のコンディショニングに関するアンケート調査─ 石川県の中高生スイマーを対象に ─ | 奥田 鉄人・熊谷 史佳・小竹 誠 | 45 |
| 8 | 地方トップスイマーと国内トップスイマーのレース分析比較 | 山作 拓実・奥田 鉄人 | 51 |
| 9 | ストレス/リカバリー評価に着目したセルフモニタリング技法の効果─ セルフモニタリングシートによる検討 ─ | 門岡 晋・奥田 鉄人・熊谷 史佳 | 61 |
| 10 | 消費者教育における高等学校「公共」と「家庭基礎」の協働性 | 手塚 貴子 | 67 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第14巻第1号 (2020年9月発行)
| 1 | オンライン授業から形成される教員養成系学生の学び─ ロイロノート・スクールを活用した学び ─ | 清水 和久 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | アドルフォ・サルコリの音楽活動に関する研究(8)─ 1936年に書かれたサルコリ関連資料を中心に(その2) 追悼する人びと ─ | 直江 学美 | 7 |
| 3 | 学級集団の自治性の高さに応じた算数科の授業展開(2)─「 C 変化と関係」比(6学年) ─ | 森永 秀典 | 15 |
| 4 | 祭礼組織の変容─ UNESCO無形文化遺産「青柏祭の曳山行事」の事例 ─ | 大森 重宜、櫻井 貴志、佐々木 達也、西本 夏樹 | 21 |
| 5 | 夏季の野球観戦における深部体温の変化 | 加藤 慎剛、奥田 鉄人 | 31 |
| 6 | 「支えるスポーツ」からみる持続可能なスポーツイベント─ 金沢マラソン2019の応援スポット運営関係者への調査から ─ | 西村 貴之、池田 幸應 | 35 |
| 7 | フィリップ・ド=モルネー─ ユグノーによる「永遠の哲学」 ─ | 枝村 祥平 | 43 |
| 8 | Language Teaching in Japan in a Digital Age─ Issues, Considerations and Potential Pitfalls ─ | リンチ ギャビン | 51 |
| 9 | 卒業研究優秀賞報告要旨 | 馬場 治 | 57 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第13巻第2号 (2020年3月発行)
| 1 | 地方における実科高等女学校利用層の社会的性格─ 大正期の石川県能美郡立実科高等女学校入学者の分析 ─ | 井上 好人 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 中核市における児童相談所設置の可能性 | 川並 利治 | 15 |
| 3 | 学生が授業者となるワークショップ型研修の在り方─ ロイロノートを活用した「教職実践演習」の講義を通して ─ | 清水 和久 | 25 |
| 4 | アドルフォ・サルコリの音楽活動に関する研究(7)─ 1936年に書かれたサルコリ関連資料を中心に,その1 ─ | 直江 学美 | 33 |
| 5 | 小学校国語科における基本的文法事項の指導法─ 主語と述語の関係を中心に ─ | 馬場 治 | 100 |
| 6 | 保育士養成課程とキャリアアップ研修における学びの関係性 | 開 仁志 | 39 |
| 7 | 児童の情報活用能力育成に取り組む若手教員への支援─ 「RISOよみとき新聞ワークシート」を用いた指導事例や示範授業の提供を通して ─ | 細川 都司恵 | 45 |
| 8 | 小学校における望ましい教員組織を構成する要因の研究─ 理想の学級集団の集団構造を参考に ─ | 森永 秀典 | 51 |
| 9 | 第2回国民体育大会(1947年石川国体)に関する研究(2)─ 競技施設設備の整備について ─ | 大久保 英哲 | 57 |
| 10 | サッカーのヘディングが脳に及ぼす影響について | 奥田 鉄人 | 67 |
| 11 | 文字とは何か─ 書字に関する大学院生・研究者向け教科書のための研究ノート ─ | 河野 俊寛 | 71 |
| 12 | スポーツツーリズムイベントの構造分析─ 能登和倉万葉の里マラソンのマーケティング戦略 ─ | 山木 智恵子 | 77 |
| 13 | キャリア発達を支援するプログラム開発─ 基礎ゼミナールに交流分析を導入して ─ | 岡本 泰弘 | 85 |
| 編集後記 |
第13巻第1号 (2019年9月発行)
| 1 | 保育所保育指針の変遷に関する一考察 ─ 領域「環境」の保育内容に着目して ─ | 天野 佐知子 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 教科教育法の授業において大学生が行う授業リフレクションの研究 ─ 授業計画に効果的に授業リフレクションを取り入れる授業デザインの考察 ─ | 芥川 元喜 | 7 |
| 3 | 高等教育におけるタブレット端末の活用 ─ “Loilo note for school”の実践事例 ─ | 清水 和久・細川 都司恵 | 15 |
| 4 | アドルフォ・サルコリの音楽活動に関する研究(6) ─ 1933年から1935年のサルコリ関連の資料を中心に ─ | 直江 学美 | 23 |
| 5 | 学級集団の自治性の高さに応じた算数科の授業展開 ─「 D データの活用」起こり得る場合(6学年) ─ | 森永 秀典 | 31 |
| 6 | 音楽的な変化を合図とする2人組形成における相手選択と接触行動 | 連 桃季恵 | 37 |
| 7 | 第2回国民体育大会(1947年石川国体)に関する研究(1) | 大久保 英哲 | 45 |
| 8 | 大学内は禁煙化すべきか? ─ 運動部学生の喫煙率の調査と喫煙者が非喫煙アスリートに与える影響 ─ | 中田 将人・奥田 鉄人 | 53 |
| 9 | 書字の認知理論と運動理論 ─ 書字に関する大学院生・研究者向け教科書のための研究ノート ─ | 河野 俊寛 | 59 |
| 10 | 高齢者の最大下運動負荷試験における主観的疲労と生理学的負荷の個体差 | 齊藤 陽子・垣花 渉 | 65 |
| 11 | From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals ミレニアム発展目標から持続可能な発展目標へ | リンチ ギャビン・ジョマダル ナシル | 69 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第12巻第2号 (2019年3月発行)
| 1 | 教職志望の大学生における授業リフレクションの事例研究 | 芥川 元喜 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 幼稚園教育要領の変遷に関する一考察 ─ 小学校家庭科を見据えた保育内容「自然」及び「環境」─ | 天野 佐知子 | 9 |
| 3 | 石川県ユネスコ協会主催スタディツアー参加報告 ─ ベトナム・カンボジアでの体験を中心に ─ | 池上 奨・野崎 幸生 | 15 |
| 4 | 明治・大正期における「良妻賢母」主義と高等女学校生徒の実践意識 ─ 校友会活動としての「演習會」の考察から ─ | 井上 好人 | 25 |
| 5 | 中学校理科の2つのものづくり事例における 21世紀型能力の要素との関連付けの比較 | 佐藤 幸江 | 35 |
| 6 | 中核市及び特別区における児童相談所設置の意義と課題 ─ 子ども家庭支援体制の強化を目指して ─ | 川並 利治 | 39 |
| 7 | 年中児を対象とした園生活の安全指導 ─ 視聴覚教材を活用した集合教育 ─ | 北川 節子・佐藤 真由美(金沢医療技術専門学校) | 47 |
| 8 | 数学的モデリングの教材開発と評価 | 佐藤 幸江 | 53 |
| 9 | 大学における海外体験学習の効果と展望 ─ 海外悉皆研修の可能性 ─ | 清水 和久 | 59 |
| 10 | 教育心理学に関わる研究成果の活用(6) | 高 賢一 | 65 |
| 11 | アドルフォ・サルコリの音楽活動に関する研究(5) ─ 1931年から1932年のサルコリ関連の資料を中心に ─ | 直江 学美 | 69 |
| 12 | 幼児期に「育みたい資質・能力」を踏まえた「ねらい及び内容」についての考察 | 開 仁志 | 75 |
| 13 | 国際試合におけるインクルーシブスポーツの調査研究 ─ 8th INAS World Half Marathon 大会の状況 ─ | 井上 明浩 | 81 |
| 14 | 全日本学生選抜能登半島一周駅伝競走大会(1968~1977)の研究(8) ─ 第10回大会コースについて ─ | 大久保 英哲・親谷 均二・櫻井 貴志・西村 貴之・阿羅 功也・佐々木 達也 | 87 |
| 15 | 教育相談・生徒指導担当教師への児童生徒理解促進の一方途 ─ ロールレタリングの導入を通して─ | 岡本 泰弘 | 97 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第12巻第1号 (2018年9月発行)
| 1 | 小・中・高等学校家庭科における「保育領域」に関する研究 | 天野 佐知子 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 石川県の保育施設における保健活動の実態調査 2 ─ 保健担当職員,与薬,園児の健康管理 ─ | 北川 節子 | 7 |
| 3 | 2018年度 iEARN 国際会議報告 ─ iEARNアメリカ国際会議の内容と意義 ─ | 清水 和久 | 15 |
| 4 | 教育心理学に関わる研究成果の活用(5) | 高 賢一 | 21 |
| 5 | アドルフォ・サルコリの音楽活動に関する研究(4) ─ 1921年から1930年のサルコリ関連の資料を中心に ─ | 直江 学美 | 25 |
| 6 | 理科に苦手意識を持つ学生への理科教育法の実践とその評価 | 永坂 正夫 | 33 |
| 7 | 保育記録から『人間関係』を読み取る視点 ─ ラーニング・ストーリーを通して ─ | 福井 逸子 | 39 |
| 8 | リトミックにおけるグループの活用方法に関する研究 ─ リトミック指導書の比較を通して ─ | 連 桃季恵 | 47 |
| 9 | 全国高等学校野球選手権石川大会における救護症例の検討 | 石山 晃基・奥田 鉄人・成宮 久詞・間所 昌嗣・沼田 優平・下出 純央 | 53 |
| 10 | 全日本学生選抜能登半島一周駅伝競走大会(1968~1977)の研究(7) ─「 能登駅伝を語る」シンポジウム(2017)記録 ─ | 大久保 英哲・親谷 均二・櫻井 貴志・西村 貴之・阿羅 功也・佐々木 達也 | 57 |
| 11 | 姿勢に影響を与える要因の検討 | 太田 めぐみ・大森 重宜 | 65 |
| 12 | Developing English Language Education in the Faculty of Human Sciences | リンチ ギャビン | 71 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第11巻第2号 (2018年2月発行)
| 回顧と展望 | 大森 重宜 | ||
| 経歴と業績 | 宮﨑 正史 | ||
| 1 | 現代アートで遊ぶ ─ 画力不要のアート ─ | 池上 奨 | 1 |
| 2 | 教員養成学からみた学生の「びわ湖フローティングスクール」への支援活動の意義 ─ 社会科学習・自然体験活動・環境学習の広領域カリキュラムの実際にふれて ─ | 井上 好人 | 7 |
| 3 | 児童福祉司養成に必要な実務の専門性とスキル ─ 児童相談所スーパーバイザーの視点 ─ | 川並 利治・井上 景 | 15 |
| 4 | 石川県の保育施設における保健活動の実態調査1 ─ 園児の健康問題,健康・安全教育 ─ | 北川 節子 | 25 |
| 5 | 初任教員の研修ニーズに関する調査研究 | 佐藤 幸江 | 33 |
| 6 | 小学校英語教育の授業デザイン ─ 新学習指導要領における外国活動及び外国語科で重視すべきこと ─ | 清水 和久 | 39 |
| 7 | 教育心理学に関わる研究成果の活用(4) | 高 賢一 | 45 |
| 8 | 保育士・幼稚園教諭志望学生に対する自然や身近な動植物に親しむための教育内容の評価検討 | 永坂 正夫 | 49 |
| 9 | アドルフォ・サルコリの音楽活動に関する研究(3) ─ 1916年から1920年のサルコリ関連の資料を中心に ─ | 直江 学美 | 53 |
| 10 | 小学校国語科における地域教材活用の一方法 ─ 泉鏡花「化鳥」を中心に ─ | 馬場 治 | 108 |
| 11 | 保育内容5 領域と育みたい資質・能力の関係についての考察 | 開 仁志 | 59 |
| 12 | 戦後初期の学校における教育の理念に関する考察 | 村井 万寿夫 | 65 |
| 13 | 乳幼児を対象とする歌唱教材に関する研究 ─ 学生へのアンケート調査を通して ─ |
連 桃季恵 | 71 |
| 14 | 学生の「能登・祭りの環」インターンシップ事業における地域・大学協働に関する研究 | 池田 幸應 | 77 |
| 15 | 特別支援学校在校生・卒業生の余暇活動における縦断的事例報告 | 井上 明浩 | 83 |
| 16 | 全日本学生選抜能登半島一周駅伝競走大会(1968~1977)の研究(6) ─ 第9・10回大会の概要と競技記録 ─ | 大久保 英哲・親谷 均二・北川 潔・櫻井 貴志・佐々木 達也・西村 貴之・阿羅 功也 | 89 |
| 17 | ジュニア水球選手の筋肉発達の特徴について ─ 体組成測定による横断的研究 ─ | 奥田 鉄人・中川 明彦・山田 健二・清水 彩子・上田 さやか・須藤 明治 | 97 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第11巻第1号 (2017年9月発行)
| 1 | 文献を通してみる保育所,幼保連携型認定こども園, 幼稚園における保健活動の現状と課題 |
北川 節子 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2017年度iEARN国際会議報告 ─ iEARNモロッコ国際会議の内容と意義 ─ |
清水 和久 | 9 |
| 3 | 教育心理学に関わる研究成果の活用(3) | 高 賢一 | 15 |
| 4 | 初等音楽科教育法に関する研究(1) ─ 模擬授業に対する「心理的側面」と「基礎的な能力・知識」との比較より ─ |
直江 学美 | 19 |
| 5 | 日本における幼児教育と保育 ─ 歴史,現状と今後について ─ |
福井 逸子 | 25 |
| 6 | 第10回INAS世界知的障害者陸上競技選手権大会 の状況からみる国内外情勢 |
井上 明浩 | 31 |
| 7 | 全日本学生選抜能登半島一周駅伝競走大会(1968?1977)の研究(5) ─ 第8回大会の概要と競技記録 ─ |
大久保 英哲・親谷 均二・北川 潔・櫻井 貴志・佐々木 達也・西村 貴之・阿羅 功也 | 37 |
| 8 | ジュニア体操選手を対象とした心理サポートの事例 | 門岡 晋 | 43 |
| 9 | 中国語圏における書字研究の現状と日本語の書字検査への 応用の可能性 |
河野 俊寛 | 49 |
| 10 | サッカーJFL観戦者の観戦満足に関する調査研究 | 佐々木 達也・田島 良輝 神野 賢治 |
55 |
| 11 | Kenelm Digby’s Aristotlianism and Mechanism | 枝村 祥平 | 61 |
| 編集後記 | 馬場 治 |