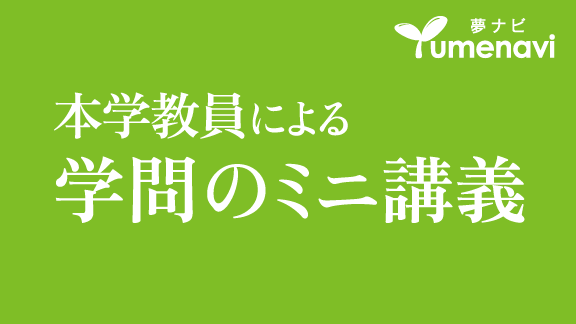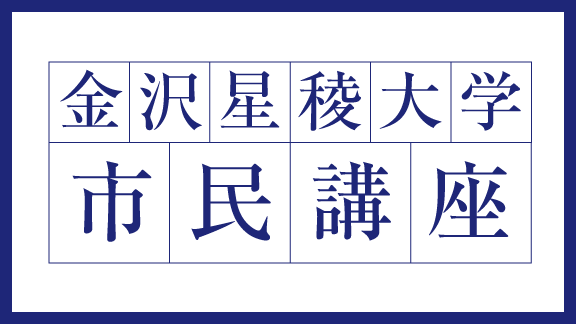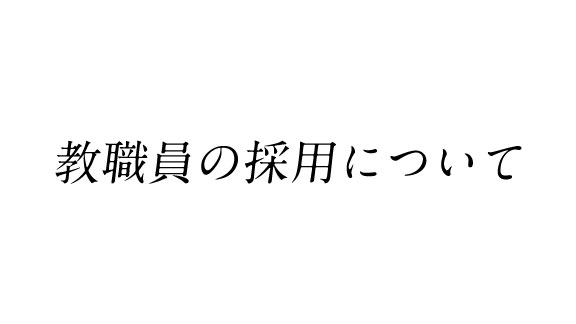人間科学研究1
人間科学研究1
第10巻第2号 (2017年3月発行)
第10巻第1号 (2016年9月発行)
| 1 | 本学の指定保育士養成課程設置に向けての調査研究 ─石川県内保育所が求める大学卒業者の保育士像─ | 北川 節子・福井 逸子 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 教育系学生の海外研修の実態 ─ 小学校教員をめざす学生のための海外研修の在り方の検討 ─ | 清水 和久 | 9 |
| 3 | 教育心理学に関わる研究成果の活用(2) | 高 賢一 | 15 |
| 4 | 思春期の心理的特徴 ─小学校5年生へのアンケート調査から─ | 寺井 弘実 | 19 |
| 5 | アドルフォ・サルコリの音楽活動に関する研究(1) ─ 1911年,1912年のサルコリ関連の資料を中心に ─ | 直江 学美 | 23 |
| 6 | 全日本学生選抜能登半島一周駅伝競走大会(1968~1977)の研究(3) ─ 第4回大会の概要と競技記録 ─ | 大久保 英哲・親谷 均二・北川 潔 | 31 |
| 7 | 海外における書字検査の現状と今後の課題 | 河野 俊寛 | 39 |
| 8 | トランポリントレーニングが若年一般成人の体力に及ぼす影響 | 勘島 遥・齊藤 陽子 | 45 |
| 9 | Education Creating Miracles for the Working Children 南アジアの経済発展における教育の役割と新たな課題 | ジョマダル ナシル | 49 |
| 10 | An Analysis of Global Tourism in the Local Area-Issues in Matching Local Services with Global Demand- | リンチ ギャビン・キーナン マイケル | 61 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第9巻第2号(2016年3月発行)
| 1 | 2015年度 金沢星稜大学人間科学部会学術講演会「小学校国語科における読解指導のポイントと絵本の活用」 | 折川 司(金沢大学学校教育系教授) | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2015年度 人間科学部会シンポジウム 保育の魅力 ─ 子どもの生活に寄り添う保育 ─ | 開 仁志 | 7 |
| 3 | 子ども・子育て支援における市町村の役割と多機関協働に関する一考察 ─ A町における実践を通して ─ | 砂山 真喜子・北川 節子 | 13 |
| 4 | ICT活用を含み込んだ算数科学習指導の効果 ─ 小学校第2学年単元「三角形と四角形」 ─ | 佐藤 幸江 | 19 |
| 5 | 教育心理学に関わる研究成果の活用(1) | 高 賢一 | 25 |
| 6 | 幼児教育実習での経験録をもとにする調査 | 開 仁志 | 29 |
| 7 | 総合的学習の展開を阻害する要因についての検討(3) ─ 評価の方法に焦点化して ─ | 村井 万寿夫 | 33 |
| 8 | 小学校国語科における読書指導の一方法 ─ リンカーンの伝記を中心に ─ | 馬場 治 | 94 |
| 9 | 2015スペシャルオリンピックス夏季世界大会・ロサンゼルスの状況と国内未普及競技の展望 | 井上 明浩 | 39 |
| 10 | 全日本学生選抜能登半島一周駅伝競走大会(1968.1977)の研究(2) ─ 第1・2・3回大会の概要と競技記録 ─ | 大久保 英哲・親谷 均二・北川 潔 | 47 |
| 11 | 女子短大生における書字速度、学力、自己効力感、コーピングスキルの関連 | 河野 俊寛・辰島 裕美 | 57 |
| 12 | 日本によるボランティア活動のソーシャル・インパクトと今後の課題 Social Impact of Japan’s Volunteer Activities and New Challenges | ジョマダル・ナシル | 65 |
| 13 | When Did Leibniz Rehabilitate Substantial Forms? いつライプニッツは実体的形相を復興したのか? | 枝村 祥平 | 75 |
| 14 | International Communication Through Online Accommodation Services オンライン宿泊サービスにおける国際コミュニケーション | リンチ ギャビン | 81 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第9巻第1号(2015年9月発行)
第8巻第2号(2015年3月18日発行)
| 1 | 介護等体験における学生の自己意識の変化について | 佐藤 幸江 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 「国際ボランティア演習」参加学生の意識の変容 ─フィリピンの貧富の差の体験を通して─ | 清水 和久 | 5 |
| 3 | 子どもの生きる力を育てるソーシャルスキルの推進 | 高 賢一 | 9 |
| 4 | 就学前までに獲得したい力 ─小学校1年生担任への調査から─ | 寺井 弘実 | 13 |
| 5 | 保育実習Ⅱにおける経験録(試案) | 開 仁志 | 17 |
| 6 | 総合的学習の展開を阻害する要因についての検討(1) | 村井 万寿夫 | 23 |
| 7 | 地域環境を活かした大学生との協働による野外教育推進策の検討 | 池田 幸應 | 29 |
| 8 | 国際試合におけるインクルーシブスポーツの調査研究 ─Sainsbury’s Birmingham Grand Prix大会の状況─ |
井上 明浩 | 35 |
| 9 | 知的障害児における文字の読み書きに関する認知特性 ー事例調査による予備的研究ー | 河野 俊寛・嶋 美紀 | 41 |
| 10 | Education Creating Miracles for the Working Children ─A Case Study on Working Children of South Asian Countries─ | ジョマダル ナシル | 45 |
| 11 | Was Leibniz Committed to Necessitarianism in Some Part of De Summa Rerum? | 枝村 祥平 | 57 |
| 12 | 英語教育における意味解釈指導の再考 ─語用論的能力の構築について─ | 岡本 芳和 | 63 |
| 13 | 外国人留学生の言語意識についての現状調査(2) ─平成24年度国語に関する世論調査に連動して─ | 中村 朱美 | 67 |
| 14 | Syntactic Positions of Nominative Objects in Japanese ─Te-Aru Constructions─ | 森 延江 | 73 |
| 15 | Traditional Methods Trump ICT in Students’ International Communication | リンチ ギャビン | 77 |
| 16 | 平成版「ががのとかるた」作成の試み ─地域教材開発をめざす言語活動として─ | 馬場 治 | 88 |
第8巻第1号(2014年9月30日発行)
| 1 | 障害児施設の動向と保育士養成の課題 ─開設予定の指定保育士養成課程施設実習を中心にして─ | 北川 節子 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 短期語学留学生受け入れによる波及効果と今後の展望 ─ミンダナオ国際大学生の受け入れを通して─ | 清水 和久 | 7 |
| 3 | 学校心理士の意義と役割に関する考察 | 高 賢一 | 13 |
| 4 | フィリピンにおけるアドルフォ・サルコリの演奏活動 ─1910年末から1911年の新聞記事より─ | 直江 学美 | 17 |
| 5 | 幼児教育実習における経験録(試案) | 開 仁志 | 23 |
| 6 | 学会誌に見る過去10年の総合的学習における研究動向についての考察 | 村井 万寿夫 | 29 |
| 7 | 体育での学び合いによって芽生えた体育科への興味に関する研究 ─小学校教員志望の女子学生に着目して─ | 丸井 一誠 | 35 |
| 8 | 中央競技団体におけるインクルーシブスポーツの現状 | 井上 明浩・神野 賢治 | 41 |
| 9 | 音楽療法を施行した慢性疼痛患者の1例 ─受容的音楽療法(モーツァルト療法)効果による唾液中IgAの変動について─ | 奥田 鉄人・東野 千夏・北本 福美・和合 治久 | 47 |
| 10 | 知的障害児への文字の読み書き指導研究の動向 | 河野 俊寛 | 51 |
| 11 | 金沢市における女性の運動・スポーツ実施状況に関する調査研究 ─運動・スポーツ実施状況の分析と検討─ | 櫻井 貴志・田島 良輝・神野 賢治・山木 智恵子・佐々木 達也 | 57 |
| 12 | 実体の集合体は表象する精神の内にあるのか? ─ライプニッツにおける集合体の精神依存性─ | 枝村 祥平 | 65 |
| 13 | ヴィゴツキーの内言と外国語学習 ─日本語話者の英作文学習を例として─ | 川村 義治 | 71 |
| 14 | 外国人留学生の言語意識についての現状調査(1) ─平成24年度国語に関する世論調査に連動して─ | 中村 朱美 | 75 |
| 15 | 語彙動詞統語構造における統率 ─統語項-アクションサート呼応仮説─ | 森 延江 | 81 |
| 16 | プロジェクトワークを通して若者の声を重視する ─シンガポールモデルから学べること─ | リンチ・ギャビン | 83 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第7巻 第2号(2014年3月発行)
| 1 | 2013年度 人間科学部会学術講演会 和久洋三 先生「子どもの目が輝くとき?─創造力は生きる力─」 | 福井 逸子 抄録 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 『当世書生気質』にみる明治十年代の学生の“憧れ”と“不安” ─「江戸」の空間を彷徨する上京インテリ学生たち─ | 井上 好人 | 5 |
| 3 | 英作文指導における一つの糸口 ─?「なる」言語から「する」言語への転換─ | 川村 義治 | 13 |
| 4 | 社会的養護の動向と保育士養成の課題 ─開設予定の指定保育士養成課程施設実習を中心にして─ | 北川 節子 | 17 |
| 5 | 教員養成課程の学生のICT活用指導能力の現状と課題 | 佐藤 幸江 | 23 |
| 6 | 国際ボランティア講座開設の意義と実際の展開 ─フィリピン国際ボランティア演習を通して─ | 清水 和久 | 29 |
| 7 | 学校教育相談の意義と課題に関する考察 | 高 賢一 | 39 |
| 8 | 「こども相談室」での取り組み ─幼稚園での2年間の実績と課題─ | 寺井 弘実 | 47 |
| 9 | 活用力を高めるためにタブレット端末を活用する授業デザインの検討 | 村井 万寿夫 | 51 |
| 10 | 『おくのほそ道』と自作俳句 ─総合教育科目における学習意欲を高める試み─ | 馬場 治 | 82 |
| 11 | スウェーデンのトップレベル陸上クラブチームにおけるトレーニング ─ヤニック・トレガロのコーチング哲学と理論─ | 杉林 孝法 | 51 |
| 12 | 石川県におけるウィンタースポーツ実施に関する研究 | 山木 智恵子・田島 良輝・神野 賢治・櫻井 貴志・池田 幸應 | 57 |
| 13 | 初期ライプニッツの「観念論」 ─1672年の運動・物体論─ | 枝村 祥平 | 67 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第7巻 第1号(2013年9月発行)
| 1 | 算数科学習指導における思考過程を可視化する「ふきだし法」の事例研究 | 佐藤 幸江 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 国際協働学習への校種別取り組み比較 ─活動のねらいと成果の観点から─ | 清水 和久 | 7 |
| 3 | 教育相談を生かした学校経営に関する考察 | 高 賢一 | 13 |
| 4 | アメリカにおけるICT活用教育の現状 ─教科の学習指導における日本とアメリカとの比較─ | 村井 万寿夫 | 17 |
| 5 | 第9回INAS世界知的障害者陸上競技選手権大会の状況からみる国内外情勢 | 井上 明浩 | 23 |
| 6 | 金沢市のスポーツ振興施策に資する「運動・スポーツ実施状況」の分析と検討 ─石川県民の運動・スポーツ活動状況調査をもとに─ | 神野 賢治・田島 良輝・櫻井 貴志・山木 智恵子・池田 幸應 | 29 |
| 7 | 社会人野球選手の打撃動作における、左右打者間のキネマティクス的相違に関する事例的研究 | 下山 優・島田 一志・新井 祐稀・長谷川 大介・川村 卓・奈良 隆章・名古屋 光彦 | 39 |
| 8 | 自立・持続経営を担保する総合型地域スポーツクラブの財務分析に関する研究 | 田島 良輝・谷畠 範恭・神野 賢治・西村 貴之・佐川 哲・奥田 睦子 | 43 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第6巻 第2号(2013年3月発行)
| 1 | 2012年度 人間科学会学術講演会 オリンピックとスポーツ心理学 | 石村 宇佐一・村山 孝之・櫻井 貴志 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 大正・昭和初期の粟崎遊園にみる娯楽と身体表象 ─『北國新聞』記事を中心とした分析─ | 井上 好人 | 5 |
| 3 | 英語学習者の視点から見た副詞outの多義とその理解 | 川村 義治 | 13 |
| 4 | 国際交流学習のための研修プログラムの開発 ─教師向けワークショップ型コースを通して─ | 清水 和久 | 19 |
| 5 | 教師の聴く力に関する考察 | 高 賢一 | 23 |
| 6 | 音と人間 ─その関わりについての考察─ | 谷中 優 | 27 |
| 7 | 保育園における保護者支援の課題 ─保育研究大会助言者・保育研修会講師の視点から─ | 寺井 弘実 | 33 |
| 8 | ICTを活用した協働教育に関する実証的研究 | 村井 万寿夫 | 37 |
| 9 | 香港の障害者スポーツ協会に関する研究 ─香港弱智人士體育協會並びにスペシャルオリンピックス香港について─ | 井上 明浩 | 43 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第6巻 第1号(2012年9月発行)
| 1 | 画像リテラシーの育成と評価に関する実証的研究 | 岡部 昌樹・村井 万寿夫・吉田 貞介 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 理論と実践を融合させた授業の試み ─講義「特別活動の研究」を通して─ | 清水 和久 | 7 |
| 3 | 高校中途退学の予防に関する考察 | 高 賢一 | 13 |
| 4 | 石彫家・八木ヨシオの作品について ─作曲家の立場からの考察─ | 谷中 優 | 19 |
| 5 | アドルフォ・サルコリの演奏活動について ─海外を中心に─ | 直江 学美 | 29 |
| 6 | 小中一貫教育の取組の現状と課題 | 村井 万寿夫 | 35 |
| 7 | 第3回INASグローバルゲームズの状況からみる国内情勢 | 井上 明浩 | 39 |
| 8 | 七尾祇園祭にみる能登の民族スポーツ「キリコ祭り」 | 大森 重宜 | 45 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第5巻 第2号(2012年3月発行)
| 1 | 2011年度 人間科学会学術講演会 岡 朝子 先生「本は心の宝もの─こどもと読書体験─」 | 馬場 治 抄録 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 吹奏楽活動における子どもの変容について | 谷中 優 | 13 |
| 3 | ESDとしての国際交流学習の展開の可能性 ─国際交流壁画共同制作活動を通して─ | 清水 和久 | 23 |
| 4 | 不登校の子どもへの関わり方に関する考察—大学生・大学院生を中心として— | 高 賢一・古澤 賢祐 | 29 |
| 5 | エルンスト・ルードヴィッヒ・ウーライが遺したもの ─作曲と音楽教育活動からの考察─ | 谷中 優 | 33 |
| 6 | 小学校におけるデジタル教科書の現状と課題 | 村井 万寿夫 | 41 |
| 7 | 2011年スペシャルオリンピックス夏季世界大会の状況と国内未普及競技の展望 | 井上 明浩 | 45 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第5巻 第1号(2011年9月発行)
| 1 | 本学こども学科学生のキャリア形成に関する要因分析 | 北川 節子・永坂 正夫 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 吹奏楽活動における子どもの変容について | 谷中 優 | 7 |
| 3 | 東日本大震災地の学校生活 ─こどもと教師のこころの問題─ | 寺井 弘実 | 19 |
| 4 | タブレットPCと電子黒板を用いた協働教育の学習効果 | 村井 万寿夫 | 25 |
| 5 | 足把持力がスプリント力に及ぼす影響 | 大森 重宜・杉林 孝法・島田 一志・太田 めぐみ | 31 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第4巻 第2号(2011年3月発行)
| 1 | 金沢星稜大学人間科学会 学術講演会『いしかわジュニア競技力向上セミナー ─スポーツパフォーマンスにおける“体幹”の働きに迫る─』 | 人間科学会運営委員会 抄録 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 四高における音楽部の創設 ─石倉小三郎に集う洋楽愛好者たち─ | 井上 好人 | 7 |
| 3 | 接頭辞subの多義性 ─認知意味論の観点から─ | 川村 義治 | 13 |
| 4 | 金沢市の子育て支援に関する実態調査(4) ─かなざわ子育て夢ステーション事業─ | 北川 節子 | 21 |
| 5 | 保健室登校の子どもの支援に関する考察 | 高 賢一 | 27 |
| 6 | 日本コンピュータ音楽教育学会17年の軌跡 ─DTM活用による音楽教育の実践と推進─ | 谷中 優 | 31 |
| 7 | 日本におけるベル・カントの父,アドルフォ・サルコリの生涯 | 直江 学美 | 41 |
| 8 | 石川県の小学生と中学生の携帯電話についての意識調査 | 村井 万寿夫 | 45 |
| 9 | 大学コンソーシアム石川ゼミナール連携型事業における学生の地域連携活動 | 池田 幸應 | 49 |
| 10 | 野球の捕球動作におけるグラブ内の手指肢位の定量的分析 | 奈良 隆章・馬見塚 尚孝・川村 卓・多胡 伸哉・島田 一志 | 55 |
| 11 | 男子中学生における基礎的運動能力と重心動揺の関係 | 杉林 孝法・大森 重宜・清水 都 | 59 |
| 編集後記 | 馬場 治 | 67 |
第4巻 第1号(2010年9月発行)
| 1 | 学校教育相談における養護教諭の役割に関する考察 | 高 賢一 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 幼稚園におけるICT活用の可能性について ─創造性を育むアプローチ─ |
谷中 優 | 5 |
| 3 | 日本の演奏会プログラムより見た西洋声楽受容の一考察 | 直江 学美 | 11 |
| 4 | 電子黒板の活用 ─実践上の課題─ | 村井 万寿夫 | 29 |
| 5 | 第6回 INAS-FID 室内陸上競技世界選手権大会の状況と国内展望 | 井上 明浩 | 33 |
| 6 | 小学生野球選手における異なる形状のバットを用いた 素振り動作のキネマティクス的研究 |
奈良隆章・船本 笑美子・島田 一志・川村 卓・馬見塚 尚孝 | 39 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第3巻 第2号(2010年3月発行)
| 1 | 人間科学部こども学科公開講演会・シンポジウム「どちらになりたい? 小学校の先生・幼稚園の先生」 | 馬場 治 抄録 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 人間科学会学術講演会「子どものこころと親の役割」京都大学名誉教授 山中康裕先生 | 寺井 弘実 抄録 | 13 |
| 3 | 3年こどもフィールド演習における実践と課題 | 池上 奨・北川 節子・高垣 展代・谷中 優 | 19 |
| 4 | 金沢市の子育て支援に関する実態調査(3) ─0,1歳児を持つ母親の支援等に関する自由記述の分析─ | 北川 節子 | 27 |
| 5 | 公立中学校におけるスクールカウンセラーの活用に関する考察(2) | 高 賢一 | 33 |
| 6 | 現代音楽の手法による音楽教育について ─義務教育課程における実践と考察─ | 谷中 優 | 37 |
| 7 | 不登校生徒との2年間の関わり ー攻撃性表出の重要性ー | 寺井 弘実 | 43 |
| 8 | 日本の演奏会プログラムより見た西洋声楽受容の一考察 | 直江 学美 | 47 |
| 9 | 小学校の授業における“活用力”に関する実践的研究 ー知識と技能の確実な習得とそれらを活用する能力についてー |
村井 万寿夫 | 51 |
| 10 | 2009スペシャルオリンピックス冬季世界大会の状況と今後の国内の展望 | 井上 明浩 | 57 |
| 11 | 〈資料〉金沢市内における公共スポーツ施設の利用実態調査報告 | 神野 賢治・田島 良輝 | 63 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第3巻 第1号(2009年9月発行)
| 1 | 地域と学生 ─ラ・フォル・ジュルネにおける学生参画の提案─ | 池上 奨・直江 学美・高山 奈津紀・寺口 正義・小林 明喜子 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 菊池幽芳・新聞連載小説「寒潮」に表象された四高生と女学生の恋愛 | 井上 好人 | 7 |
| 3 | 金沢星稜大学遠隔授業システムの有効活用による実践的な研究 ─教授・学習行動の改善による相互交渉性の促進─ | 岡部 昌樹 | 15 |
| 4 | 金沢市の子育て支援に関する実態調査(2) ─0,1歳児をもつ母親の属性及び情報収集と支援の利用─ | 北川 節子 | 21 |
| 5 | 公立中学校におけるスクールカウンセラーの活用に関する考察(1) | 高 賢一 | 29 |
| 6 | 即興表現における実践と考察 | 谷中 優 | 33 |
| 7 | コミュニケーションカードによる効果的な教授法について ─学生と意思疎通を図るためのLCカードの活用─ | 村井 万寿夫 | 39 |
| 8 | 独立系プロスポーツリーグ観戦者の観戦満足に関する調査研究 ─08年石川ミリオンスターズのホームゲーム観戦者を事例として─ | 田島 良輝・神野 賢治・岡野 紘二 | 47 |
第2巻 第2号(2009年3月発行)
| 1 | 金沢星稜大学人間科学会 学術講演会 『オリンピックフォーラム』 | 大森 重宜 抄録 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 画像リテラシーを育成するトレーニングパッケージの開発と授業試行 | 岡部 昌樹 | 17 |
| 3 | 金沢市の子育て支援に関する実態調査( 1 ) —子育てサロンを利用する核家族で乳児をもつ母親からの聞き取り— | 北川 節子 | 23 |
| 4 | ひきこもりの具体的対応法に関する考察 | 高 賢一 | 31 |
| 5 | サウンドスケープにおける理論と実践 | 谷中 優 | 35 |
| 6 | 育児不安を抱える母親支援果 —虐待行為に至った母親の面接からの考察— | 寺井 弘実 | 41 |
| 7 | 本学1年次生の情報処理の能力と知識についての比較研究 | 村井 万寿夫 | 47 |
| 8 | 公共スポーツサービスの利用者に関する研究 ─利用者の特性と満足度に着目して─ | 神野 賢治・ 田島 良輝・井上 明浩 | 53 |
| 9 | 地域プロスポーツクラブ観戦者の顧客満足に関する調査研究 ─08年 ツエーゲン金沢のホームゲーム観戦者を事例として─ | 田島 良輝・神野 賢治・岡野 紘二 | 63 |
第2巻 第1号(2008年9月発行)
| 1 | 幼児期からのピアノレッスンによって身体化された文化資本のゆくえ | 井上 好人 | 1 |
|---|---|---|---|
| 2 | ID理論を取り入れた授業設計手順の開発 | 岡部 昌樹 | 7 |
| 3 | 「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」についての一考察 | 曽我 千春 | 13 |
| 4 | ひきこもりのプロセスと心理に関する考察 | 高 賢一 | 19 |
| 5 | 現代音楽における方法論についての考察 | 谷中 優 | 23 |
| 6 | 小学生がICTメディアを学ぶためのシミュレーター教材の開発 | 村井 万寿夫 | 29 |
| 7 | 地域プロサッカークラブの観戦者に関する調査研究 —ツエーゲン金沢のホームゲーム観戦者を事例として— | 神野 賢治・田島 良輝・岡野 紘二 | 35 |
| 編集後記 | 馬場 治 |
第1巻 第1号(2008年3月発行)
| 創刊の辞 | 宮﨑 正史 | ||
| 1 | 馬場 治 抄録 | 1 | |
| 2 | The Reconsideration of the Viewpoint to discuss Media Education | 岡部 昌樹 | 5 |
| 3 | 川村 義治 | 13 | |
| 4 | 北川 節子 | 19 | |
| 5 | 曽我 千春 | 27 | |
| 6 | 金沢星稜大学における学生相談体制の推進に関する研究 | 高 賢一 | 33 |
| 7 | 創造的音楽教育について ーコンピュータによる表現活動ー | 谷中 優 | 39 |
| 8 | 現代の子育て支援の専門性 | 寺井 弘実 | 45 |
| 9 | 底泥無機態リン源の違いがコカナダモの成長に及ぼす影響 | 永坂 正夫 | 51 |
| 10 | 「いじめ問題」についての教師の意識と指導に関する研究 | 村井 万寿夫 | 55 |
| 11 | 剣道の踏み込み距離(間)に関する研究 | 惠土 孝吉・星川 保 | 63 |
| 12 | 統廃合小学校児童の日常歩行距離 | 大森 重宜・清水 都 | 67 |
| 13 | 野球のバッティングにおけるバットの握り位置の相違がスイングに与える影響 | 島田 一志・田畑 広樹・川村 卓 | 71 |
| 編集後記 | 馬場 治 |